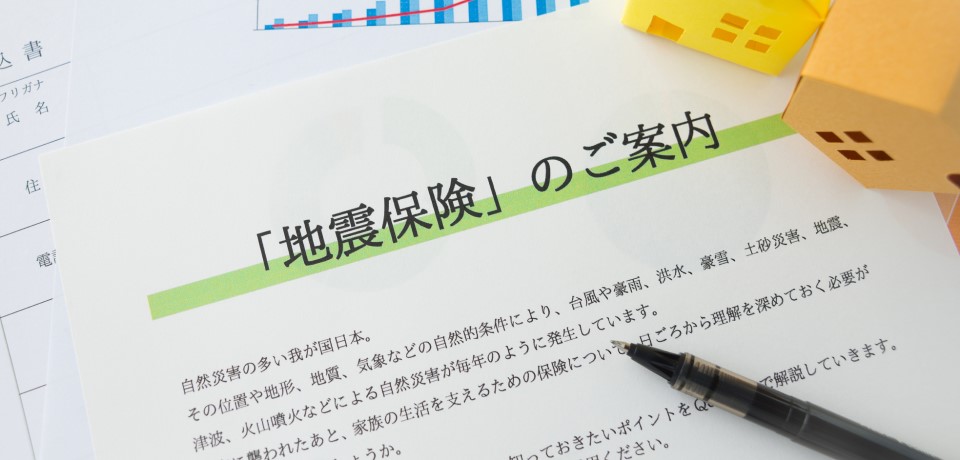
不動産投資に地震保険は必要?相場や補償内容について解説
地震の多い日本において、建物や家財の破損リスクに備えることは、不動産の貸主にとって非常に重要です。では、不動産投資を行う際には、地震保険に加入すべきなのでしょうか?この記事では、地震保険の必要性や、補償内容、保険料の相場などについて解説します。
目次
不動産投資における地震保険
地震保険とは、地震と、それに伴って発生した津波や火災などの二次災害による損害を補償する保険です。しかし、マンションやアパートの賃貸経営を行う際、火災保険には加入しても、地震保険には加入しない貸主(オーナー)は少なくありません。これから賃貸経営を行う方のなかにも、加入を迷っている方がいるかもしれませんが、日本における地震リスクを考えると、地震保険による備えをしておいたほうが安心だといえます。
そこで今回は、マンションをはじめとした不動産投資を行っている貸主に向けて、地震保険についての基礎知識やその必要性、保険金額の目安などについて詳しく解説します。

不動産投資で地震保険が必要な理由
日本は地震の多い国であり、記憶に新しい2024年の石川県能登半島地震や、2018年の北海道胆振東部地震、2016年の熊本地震など、最大震度7を記録する大規模な地震を経験してきました。そのほかにも全国各地で最大震度5を超える地震が頻発しており、その被害は多くの住宅に及んでいます。たとえば、2011年に発生した東日本大震災では、住宅や店舗などの建物の被害が最も多く、10兆4,000億円もの被害額が記録されています。※1
●日本付近で発生した主な被害地震(平成8年以降)についてはこちら
また、近い将来、南海トラフ地震や首都直下地震の発生が予測されており、現在国を挙げてさまざまな対策が講じられています。※2 ですが、被災時の国の支援は、不動産の居住者に対するものが多く、貸主に対しての公的支援は少ないため、自ら地震のリスクに備えておく必要があるのです。

地震保険の補償内容
地震保険の補償の対象は、居住用の建物(マンションの共用部分を含む)と家財までです。住居として使用されない建物や、30万円を超える貴金属・宝石、通貨、有価証券(小切手、株券等)、切手、自動車などは対象外となるので、あらかじめ注意しましょう。
地震保険の特徴
地震保険は、地震保険に関する法律に基づき、政府と損害保険会社が共同運営していることが特徴です。地震保険の契約を行うのは民間の損害保険会社ですが、政府が保険金の一部を負担する仕組みになっているため、公共性の高い保険です。ここからは、具体的にどのように加入するのか、どれくらいの金額が補償されるのかについて説明します。
加入方法
地震保険は単独での契約はできず、加入する際は火災保険に付帯させる形での契約となります。なお、既に火災保険に入っている場合は、契約期間の途中からでも地震保険に追加で加入することが可能です。
保険金額
地震保険の保険金額(補償金額)は、以下のような制約が設けられています。
・保険金額は火災保険の契約金額の30~50%の範囲内
・建物の保険金額は5,000万円以内
・家財の保険金額は1,000万円以内
この制約があるのは、保険の目的が建物の再建ではなく、被災者の生活の安定であるためです。よって、建物が全壊したとしても、5,000万円を超える金額は補償されません。
保険金額は、以下の表のように損害の程度によって決まります。
| 損害の程度 | 保険金額 |
|---|---|
| 全損 | 保険金額の100%(時価額が限度) |
| 大半損 | 保険金額の60%(時価額の60%が限度) |
| 小半損 | 保険金額の30%(時価額の30%が限度) |
| 一部損 | 保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
●地震保険について詳しくはこちら

保険料の相場
前述の通り、地震保険は公共性が高いため、どの損害保険会社で契約しても、保険料は一律であるのが特徴です。ただし、建物がある地域(都道府県)や、建物の構造によって保険料(保険料率)が変わります。以下の表を参考にしましょう。※3
地震保険の基本料率(令和4年10月1日以降保険始期の地震保険契約)
| 都道府県 | イ構造 (主として鉄骨・コンクリート造建物等) | ロ構造 (主として木造建物等※) |
|---|---|---|
| 北海道・青森・岩手・秋田 山形・栃木・群馬・新潟 富山・石川・福井・長野 岐阜・滋賀・京都・兵庫 奈良・鳥取・島根・岡山 広島・山口・福岡・佐賀 長崎・熊本・大分・鹿児島 | 7,300円 | 1万1,200円 |
| 宮城・福島・山梨・愛知 三重・大阪・和歌山・香川 愛媛・宮崎・沖縄 | 1万1,600円 | 1万9,500円 |
| 茨城・徳島・高知 | 2万3,000円 | 4万1,100円 |
| 埼玉 | 2万6,500円 | 4万1,100円 |
| 千葉・東京・神奈川・静岡 | 2万7,500円 | 4万1,100円 |
※「耐火建築物」、「準耐火建築物」および「省令準耐火建物」等に該当する場合は「イ構造」
※保険金額1,000万円あたり保険期間1年につき (単位:円)
加えて、建築年または耐震性能により、居住用建物および家財に対して10~50%の割引が適用されるケースもあります。具体的な保険料は自分でシミュレーションできるので、下記リンクを参考に行ってみましょう。
●地震保険の保険料の試算についてはこちら
地震保険に加入するメリット
地震保険に加入するメリットとして、主に以下の3つが挙げられます。
・ローン返済や修繕費用に充てられる
・保険料を経費計上できる
・売却時に解約払戻金を受け取れる
ローン返済や修繕費用に充てられる
地震保険に加入していれば、建物が損壊したとき、保険金を住宅ローンの返済や建物の修繕に充てることが可能です。
地震による建物の損傷がひどい場合、賃貸に出せないだけでなく、売却することすらも難しくなります。さらに、修繕には多額の費用がかかるため、物件購入のためのローン支払いが終わっていない多くの貸主にとっては、ローンの返済と修繕費の捻出が大きな負担となります。経済的負担を軽減するためには、地震保険に加入することが有効といえるでしょう。

保険料を経費計上できる
2007年1月に創設された地震保険料控除制度により、1年間で地震保険に支払った分は全額経費として計上し、税額を控除できるようになりました。これにより、所得税では最高5万円、住民税で最高2万5,000円を控除できるため、税負担の軽減につながります。なお、数年分の保険料を一括払いしていた場合は、払い込んだ保険料を対象期間(年数)で割り、1年分に換算した額が毎年の控除対象額となります。
●地震保険料の控除について詳しくはこちら
売却時に解約払戻金を受け取れる
投資用の不動産を売却する際は、保険を解約する必要があります。火災保険と、付帯されている地震保険を途中で解約した場合、残りの契約期間(残存期間)に応じて払い戻し(返金)を受けられます。残存期間が1か月を切っている場合は払い戻しを受けられませんが、保険料の払い損にならないのは大きなポイントといえるでしょう。
地震保険の注意点
前述の通り地震保険にはメリットがある一方、注意しなければならない点もあります。以下で説明します。
構造・地域によって保険料が高額になる
これまで、地震保険の保険料には損害保険会社による差がないことをお伝えしました。ですが、地震の発生リスクが高い地域や、主に木造の、免震構造でない建物の場合は保険料が高くなるケースもあるので注意が必要です。具体的には、最も高い地域で約4万円、低い地域では約1万円と4倍もの差が発生しています。
また、近年では地震保険料の改定が段階的に実施されており、保険料が値上がりの傾向にある点にも気を付けなければなりません。直近では、2021年1月に保険料の改定が行われ、全国平均で5.1%の値上げが実施されました。そのため、この先も地震保険料が値上げされ、負担が増えていく可能性は否めません。

損害が全額補償されるとは限らない
前述の通り、地震保険の補償金額には制限があり、損害の全てが補償されるわけではないことにも注意が必要です。損害の状態、規模によっては保険でカバーしきれず、自己負担が必要なケースも出てくることを頭に入れておきましょう。
地震保険に加入してリスクに備えた賃貸経営をしよう
ここまで、賃貸経営における地震保険の必要性、地震保険の特徴や保険料について解説してきました。地域や物件の構造によって保険料が高くなることを懸念する方もいらっしゃるかもしれません。しかし、地震は建物や家財に甚大な被害をもたらすうえ、被害額が巨額です。こうしたリスクに備え、安心して賃貸経営をするためにも、地震保険に加入することを早めに検討しましょう。
三井のリハウスでは、物件を貸したいオーナーさまへ向けて、市場ニーズや地域、物件に合わせたサポートを行っています。賃貸経営に関する初歩的なサポートから、日々の賃貸管理で生まれるお悩みの解決まで、お客さまに寄り添ったサービスを提供いたします。賃貸経営についてのご相談、ご質問は、ぜひ一度三井のリハウスにお問い合わせください。
●賃貸経営をご検討の方はこちら
●近隣の賃貸物件の相場を知りたい方はこちら
●賃料査定のお問い合わせはこちら
※1出典:「平成28年版 防災白書|附属資料19 東日本大震災における被害額の推計」、内閣府
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h28/honbun/3b_6s_19_00.html
(最終確認:2024年8月30日)
※2出典:「南海トラフ巨大地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害と対策に係る映像資料」、内閣府
https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/nankai_syuto.html
(最終確認:2024年8月30日)
※3出典:「地震保険の基本料率(令和4年10月1日以降保険始期の地震保険契約)」、財務省
https://www.mof.go.jp/policy/financial_system/earthquake_insurance/standard_premiums.html
(最終確認:2024年8月30日)









