
マンションの耐用年数(寿命)は何年?長く住める物件のポイントや売却時の注意点を解説
マンションの実質的な耐用年数は、主に法定耐用年数と経済的な寿命によって決まります。この記事ではマンションのさまざま耐用年数の定義を踏まえたうえで、長く住めるマンションを選ぶ際のポイントについても解説していきます。
目次
マンションの耐用年数とは?
マンションの耐用年数とは、住居としての性能・価値を十分に発揮できるであろうと考えられている期間のことを指します。なかでも、代表的なマンションの耐用年数は以下の3つです。
・法定耐用年数
・物理的耐用年数
・経済的耐用年数
この記事ではそれぞれについて順番に解説していきます。

法定耐用年数
マンションの法定耐用年数は、一般的な鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC造)の場合は47年となっています。
法定耐用年数とは、使用・経年によって減少する資産の価値が、何年で0になるかを定めた指標です。国税庁が定めたものであり、マンションや一戸建てなどの不動産のみならず、自動車や家具、工具などにも存在します。
なぜこの法定耐用年数が設けられているかというと、減価償却を行うためです。減価償却とは、マンションをはじめとする固定資産(土地を除く)の取得時に一括して経費計上するのではなく、取得価格を法定耐用年数で割り、毎年取得価格から差し引く会計処理のことを指します。
法定耐用年数についての詳細や、不動産減価償却の計算方法については、以下の記事をご確認ください。
物理的耐用年数
物理的耐用年数とは、マンションの物理的な寿命のことを指します。マンションの物理的な寿命を建材の寿命であると仮定した場合、国土交通省によれば、鉄筋コンクリートの寿命は約120年、適切な延命措置を施せば150年ともいわれています。※1
とはいえ、マンションの寿命は建材や仕上げの質、構造、配管・配線の劣化度合いなどにも左右されるため、実際の寿命は上記より短くなると考えられるでしょう。
ここで注意したいのが、マンションの耐震基準です。マンションの耐震基準は、1950年の建築基準法で制定されて以降、1981年と2000年、2007年に見直されており、新しい耐震基準であればあるほど、建物に要求される耐震性は上がるため、地震による建物へのダメージが少なくなっています。地震の多い日本では、耐震性は建物の物理的な寿命を左右するでしょう。

経済的耐用年数
経済的耐用年数とは、マンションを経済的な観点から見た場合の寿命のことです。不動産としての資産価値や、経済的な効果が期待できなくなる時点が寿命とされています。
実際、国土交通省の「期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値向上について」によれば、RC造住宅の平均寿命(区間残存率が50%となる期間)は、68年とあります(2011年調査)。※1この背景としては、経年に伴う資産としての魅力度が相対的に低下し、建物を維持することよりも、建て替えといった手段を取ったほうが経済的な観点からプラスであると考えられるためです。
これらの理由から、現実的なマンションの寿命とは、経済的な価値が残っている期間であると考えられるでしょう。
マンションが法定耐用年数を超えたらどうなる?
マンションが法定耐用年数を経過した場合、以下の点に注意が必要です。
・減価償却の期間が短くなる
・住宅ローンが組みにくい
ここではそれぞれの注意点について順番に解説します。
減価償却期間が短くなる
賃貸経営といった投資目的でマンションを購入しようと考えている場合、法定耐用年数をすぎているマンションは減価償却できる期間が短くなる点に注意しましょう。
前述の通り、事業用にマンションを購入した際の取得費用は、購入した年に全額を支出として計上するのではなく、取得金額を法定耐用年数で均等に割って毎年支出として計上します。この会計処理による毎年の支出を減価償却費といいます。収入から減価償却費を差し引くことで、収入にかかる税金を減らせるため、長期的な節税が可能になるという仕組みです。
法定耐用年数が既に経過しているマンションの場合は、法定耐用期間の20%(端数は切り捨て)を残りの耐用年数と見なして減価償却すると決められています。たとえば、法定耐用年数を超えたRC造住居用マンションは、もともとの耐用年数は47年なので、減価償却できる期間は9年となります。
加えて、築年数がそれなりに経過しているマンションだと、高額な家賃収入も期待しにくいという注意点もあります。購入する際は、家賃収入に対して維持管理費や税金などの支出のバランスが適切であるか考慮しましょう。
住宅ローンが組みにくい
融資を受ける場合、融資期間を「法定耐用年数 - 経過年数」で決める金融機関があります。住宅ローンを組む際には該当のマンションを担保とすることが一般的で、万が一ローンの支払いができなくなった場合、裁判所経由でその物件を競売(けいばい)にかけることで金融機関側の融資額は補償されます。
しかし、法定耐用年数を超えている物件では、売却しても金融機関側の損失を埋めることができない可能性が高くなります。結果として、耐用年数をすぎたマンションはローンの審査が通りにくくなるのです。
マンションの寿命を左右する要素
マンションの寿命を左右する要素は、耐久性のほか以下の3つが挙げられます。
・維持管理の状態
・耐震性能
・立地
マンションを購入する際は、これらのポイントをよく確認しましょう。
維持管理の状態
適切なメンテナンスが行われていればマンションの耐久性が維持できるため、物理的寿命も長くなります。外壁のコンクリートやタイル、共用部分、配管などがメンテナンス箇所の例です。
現在お住まいの中古マンションのメンテナンス状況が心配な方は、管理組合へ確認してみるとよいでしょう。マンション購入前の方は、不動産会社に確認してみることをおすすめします。
マンションではこうした定期的なメンテナンスを行うための大規模修繕に備えて「修繕積立金」を徴収しています。現在マンションに住んでいる方は、修繕計画がきちんと行われているか、積立金に不足がないかなどを確かめるのも大切です。また、これから中古マンションを購入する方は、大規模修繕がいつ行われたか、それ以外にどのような修繕履歴があるかを不動産会社に確認しておくと安心でしょう。

耐震性能
先述の通り、日本では地震による建物の倒壊が多く、建築基準法により耐震基準が定められています。耐震基準とは、地震が起きても倒壊または損壊しない住宅を建築するため、1981年6月に建築基準法施行令を改正して定められた基準のことです。1981年5月までの旧耐震基準では「震度5強の揺れでほとんど損傷しない水準」とされていましたが、新耐震基準では、「震度6強~7程度の揺れでも倒壊しない水準」に変更されました。
なかには、旧耐震基準で建てられている中古マンションもありますが、そのような物件は現在の耐震基準で建築されたマンションに強度の面で劣るため、震災リスクに脆弱だといえます。マンションを購入する際は必ず、耐震基準について不動産会社に確認するようにしましょう。
立地
一般的なマンションの場合、築年数に応じて資産価値は減少していきます。しかし、都市部や主要駅の近くなどの好立地にあるマンションは、住宅需要に対して供給戸数が少ないため、築年数が経過しても資産価値が下がりにくいという特長があります。このようなマンションの場合、経済的な寿命は長いといえるでしょう。
耐用年数の長いマンションを見極めるポイント
なるべく耐用年数の長いマンションを購入したい場合は、以下の2つを心がけましょう。
・住宅性能評価書を確認する
・安心R住宅を選ぶ
住宅性能評価書を確認する
「住宅性能評価書」とは、住宅性能表示制度により、マンションや一戸建ての建物の性能について第三者機関が評価した内容を表示した書面のことです。評価を行う第三者機関は国土交通大臣によって登録された機関で、全国共通のルールにのっとって公平に評価しています。
評価基準には、耐震性や、配管の点検・交換の維持管理・更新などが含まれます。また、これらの書面において建物の寿命を測る際には、「劣化対策等級」という項目に注目してみましょう。これは、建物を長持ちさせるための対策がどの程度行われているかを、3段階の等級で評価するものです。
・劣化対策等級3:「75~90年にわたって大規模修繕が不要な対策がなされている」
・劣化対策等級2:「50~60年にわたって大規模修繕が不要な対策がなされている」
・劣化対策等級1:「建築基準法が定める対策がなされている」
ただし、上記は通常の自然条件下で日常的なメンテナンスが行われていることを前提とした基準であり、マンションの寿命を保証するものではないことに注意が必要です。
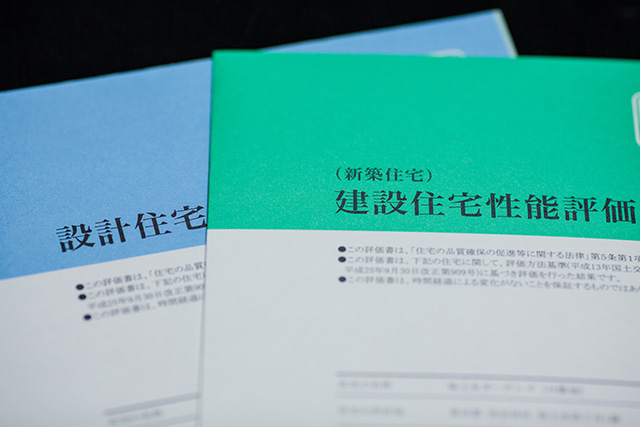
安心R住宅を選ぶ
安心R住宅とは、安心に関する一定の基準を満たす中古住宅に与えられる所定のロゴマークです。このマークの運用は、従来の中古住宅に対する、「不安」「汚い」といったマイナスイメージを払拭し、購入希望者が安心して住みたいと思える住宅を選択できるように、国土交通省の告示によって施行されました。
具体的には、以下の要件を満たすものが安心R住宅のマークを付与される物件です。
・耐震性等の基礎的な品質を備えていること
・リフォームを実施済みまたはリフォーム提案が付いていること
・点検記録等の保管状況について情報提供が行われること※2
中古マンションを購入する際は、安心R住宅に適合している物件を選ぶと適切な状態が維持されているため、安心でしょう。安心R住宅制度についてより詳しく知りたい方は、国土交通省による「安心R住宅調査報告書」を確認してみるのがおすすめです。

耐用年数が近づいたマンションは早めの売却を心がけよう
これまで、マンションの耐用年数について、法的・物理的・経済的な観点から見ていくとともに、耐用年数が迫っているマンションの注意点について見てきました。上記の理由からも、耐用年数が近づいたマンションは、耐用年数をすぎる前に売却することがおすすめです。
マンションの売却を検討している方はまず、不動産会社に査定を依頼することから始めてみましょう。三井のリハウスでは、累計取引件数100万件以上の豊富な取引実績を生かした高精度な査定を実施しております。また、査定後は全国に幅広く展開するネットワークを生かして売却活動をサポートいたしますので、マンションの売却を検討している方は、この機会に三井のリハウスをぜひご利用ください。
※1出典:期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値向上について,国土交通省
https://www.mlit.go.jp/common/001011879.pdf
(最終確認:2024年6月25日)
※2出典:安心R住宅,国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000038.html
(最終確認:2024年6月25日)


監修者:ファイナンシャル・プランナー 大石泉
株式会社NIE.Eカレッジ代表取締役。CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を保有。住宅情報メディアの企画・編集などを経て独立し、現在ではライフプランやキャリアデザイン、資産形成等の研修や講座、個別コンサルティングを行っている。










