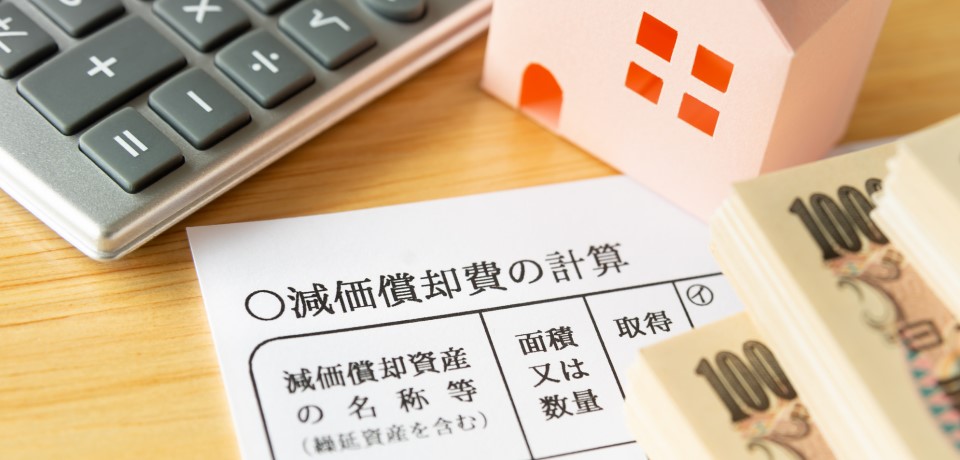
減価償却における耐用年数とは?償却率や年数表をまとめて解説
減価償却における耐用年数とは、対象となる資産で本来の用途・用法により通常予定される効果が発揮される年数のことで、減価償却費の計算に必要です。この記事では、資産ごとの耐用年数や減価償却の計算方法について詳しく解説します。
減価償却と耐用年数の関係とは?
一戸建てやマンションなどの資産を取得したときは、その価値(値段)を通常予定される耐用年数で分割し、経費として計上する減価償却を行う必要があります。この耐用年数を「法定耐用年数」といい、資産の種類によって細かく設定されています。
減価償却の仕組みは複雑ですが、知っておくと、不動産売却をするときの税の申告について理解が深まるでしょう。この記事では、減価償却や耐用年数についての基礎知識に加え、減価償却の計算方法などについて解説します。

減価償却とは
減価償却とは、長期にわたって保有・使用する固定資産の取得費用(購入金額)を、毎年の経費として計上するための会計処理のことです。
たとえば、3,000万円で不動産を購入した場合、購入金額の3,000万円全てをその年の経費として計上するのではなく、不動産を購入した日から耐用年数が終わるまで1年ずつ分割して計上します。
一戸建てやマンションなどの建物や、機械装置、器具備品などの価値は、時間の経過とともに下がっていくと考えられており、価値の減少を税務処理に反映させるための計算が減価償却です。
時間の経過とともに価値が下がると考えられている資産のことを「減価償却資産」といい、減価償却を行う際に使用する勘定科目(お金の使い道や入金の内訳を表す見出しのようなもの)を「減価償却費」といいます。減価償却資産は、取得した年だけでなく、長期にわたって価値が持続し、収益に影響を及ぼします。減価償却費を計上し、費用と収益を正確に対応させて経営状況を正しく把握しましょう。
一般的に減価償却の対象となるのは、取得価額が10万円以上で、耐用年数が1年以上あり、経年によって価値が減少すると考えられる資産です。使用できる期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものは、減価償却の対象にならず、購入した年に全額経費として計上します。
時間の経過や使用によって価値が減少しないものは対象外となり、不動産では土地が該当します。土地の値段は変動するものの、経年によって価値そのものは下がらないと考えられているため、減価償却の対象とはなりません。
●減価償却について詳しくはこちら

減価償却が必要なケース
不動産を所有している方、売却する予定のある方は、税申告のために減価償却の仕組みを理解しておく必要があります。減価償却の計算が必要になるケースは、主に次の2つです。詳しく見ていきましょう。
賃貸収入を得ている場合
賃貸経営で得た収入は、不動産所得として確定申告を行わなければなりません。不動産所得には所得税や住民税などがかかりますが、アパートやマンションの価値の目減り分は減価償却費として、賃料収入から差し引くことができます。経理上の所得を減らすことで節税につながるので、忘れずに計上することが大切です。
不動産を売却する場合
不動産を売却して得た利益を「譲渡所得」といい、所得税や住民税などの課税対象になります。譲渡所得を求める計算方法は以下の通りで、この計算を行う際に購入代金等から減価償却費を差し引いて取得費を求めます。減価償却費の計算方法については、後ほどご説明します。
課税譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
もし正確な取得費が分からない場合は、「売却金額の5%相当額」を概算取得費として計算することができます。しかし、概算取得費が実際の取得費よりも安い(低い)場合は、税負担が増え、損になってしまうため注意が必要です。
●譲渡所得に関する記事はこちら
●不動産売却にかかる税金に関する記事はこちら
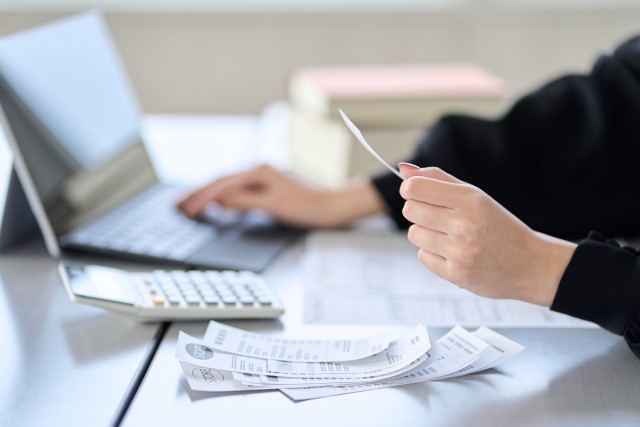
減価償却における耐用年数とは?
減価償却における耐用年数とは、法定耐用年数を指し、減価償却資産の本来の用途・用法により通常予定される効果が発揮される年数のことです。これは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)で定められています。
たとえば建物の場合、マンションに多い鉄筋コンクリート造では47年、木造住宅では22年といった耐用年数が定められています。ただし、これは税務上の基準として設けられた期間であり、建物の実際の寿命とは関係ありません。また、マイホームといった非事業用の資産と、事業用資産では耐用年数は異なり、非事業用の耐用年数は事業用の1.5倍です。

種類
法定耐用年数を含め、不動産の耐用年数には、以下の3種類があります。
・法定耐用年数
・物理的耐用年数
・経済的残存耐用年数
それぞれの特徴をまとめた表を見てみましょう。
| 耐用年数の種類 | 概要 |
|---|---|
| 法定耐用年数 | 法令で定められ、対象となる固定資産が本来の用途・用法のもとで通常予定される効用持続年数 |
| 物理的耐用年数 | 構造物の仕組みだけでなく、材質の品質が維持できなくなるなど、建物そのものが劣化して使用できなくなるまでの年数 |
| 経済的残存耐用年数 | 不動産としての経済的価値がなくなるまでの年数 |
なお、経済的残存耐用年数については、劣化の程度や建物の機能だけでなく、今後見込まれる修繕やリフォームの有無なども加味されます。
耐久年数との違い
耐久年数とは、メーカーが「問題なく使用できる」と独自に決めた年数のことです。耐用年数との違いに注意しましょう。

償却資産別の法定耐用年数
法定耐用年数は、「法定」とある通り、税法で定められた年数です。建物の構造によって年数が変わってくるため、下記の一覧表を確認しましょう。
【建物の構造別】耐用年数表
構造別耐用年数表は以下の通りです。建物の種類や構造、用途によって耐用年数が異なります。
| 建物の種類 | 構造・用途 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 一戸建て | 木造・合成樹脂造のもの・住宅用 | 22年 |
| マンション | 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの・住宅用 | 47年 |
| 木造アパート | 木造モルタル造のもの・住宅用 | 20年 |
【建物付属設備】耐用年数表
建物付属設備とは、建物の使用価値を上げる付属設備のことです。具体的にはエレベーター、冷暖房設備、自動ドアなどが挙げられます。主な建物付属設備の耐用年数は以下の通りです。
| 設備の種類 | 構造・用途 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| アーケード・日よけ設備 | 金属製のもの | 15年 |
| 店舗簡易装備 | 3年 | |
| 電気設備(照明設備含む) | 蓄電池電源設備 | 6年 |
| 給排水・衛生設備・ガス設備 | 15年 |
ここまで、償却資産別の法定耐用年数についておおまかにお伝えしてきました。建物だけでなく、建築設備、乗用車やトラックなどの車両、パソコンといった償却資産にもそれぞれ耐用年数が決められているため、より詳しく知りたい方は国税庁のホームページをご覧ください。

不動産減価償却の計算方法
ここまで、減価償却と耐用年数の仕組みについてお伝えしてきました。ここからは、不動産にかかる減価償却費の計算方法をご紹介します。
定額法と定率法
減価償却の計算方法には、「定額法」と「定率法」の2つがあり、事業用か非事業用どちらに該当するかや、物件を取得した年によってどちらを用いるかは異なります。
定額法では、固定資産の法定耐用年数の間は、毎年同じ額の減価償却費を経費として計上します。定額法の計算に必要となる項目について、以下で詳しく説明しましょう。
計算に必要な項目
定額法で減価償却費を求めるためには、「取得価額」「建物と土地の割合」「建物の法定耐用年数」「償却率」、そして「経過年数」を知っておくことが必要です。1つずつ確認していきましょう。
取得価額
減価償却費を求める場合において取得価額とは、建物の購入金額のことです。
建物と土地の割合
土地は減価償却されないため、建物と土地の取得価額を分ける必要があります。ここで問題になりがちなのが、売買契約書や譲渡対価証明書などに、建物と土地の金額が区分して記載されていない場合です。このようなケースでは、「固定資産税評価額」を参考にしたり、売買契約書の消費税から逆算したりして建物の取得価額を算出します。
物件の法定耐用年数
不動産の法定耐用年数の算出には、国税庁の「耐用年数(建物・建物附属設備)」を確認する必要があります。主な法定耐用年数は前述した通りです。
償却率
定額法か定率法どちらで計算するかや、法定耐用年数によって償却率は決まります。
経過年数
経過年数は築年数ではなく、取得してからの所有期間を指します。非事業用の場合、6か月以上の端数は1年とし、6か月未満は切り捨てて計算します。

【例】1億円の一戸建てを売却する場合の計算方法
それでは、上記の必要項目を使って実際に減価償却費を計算してみましょう。
〈例〉1億円の新築一戸建てをマイホームとして取得した場合(土地付き・2014年取得・鉄筋コンクリート造)
上記条件の場合、非事業用のため、定額法の計算式である「取得価額×0.9×償却率×経過年数」(※1)を用います。
この物件は土地付きなので、建物の取得価額を求める必要があります。売買契約書には土地5,000万円、建物5,000万円と記載されているため、建物部分の取得価額は5,000万円になります(取得に関する費用は除く)。
次に償却率を求めます。先ほどご紹介したように非事業用の場合、耐用年数は事業用の1.5倍であるため、70年となり、そこから導かれる償却率は0.015となります。経過年数は2024年時点で10年であるため、減価償却費の計算は次の通りになります。
5,000万円×0.9×0.015×10年=675万円
譲渡所得を求める際は、上記の減価償却費を購入代金等から差し引いて、取得費を算出します。なお、確定申告で計算間違いをすると修正申告の必要があり、場合によっては税が加算されることもあるため、計算を行う際の不明点や疑問は、税理士や税務署の窓口に相談しましょう。

不動産売却なら三井のリハウス
ここまで不動産に関する耐用年数や減価償却の仕組み、計算方法について解説してきました。減価償却や耐用年数について知っておくと、今後不動産売買を行うときに役立ちます。減価償却費によって譲渡所得にかかる税金も変わってくるため、この記事を参考にご自身で計算してみてください。
なお、不動産売却を考えている方は、まずは不動産会社に査定を行ってもらうとよいでしょう。三井のリハウスでは、無料査定や、そのほか売却を検討している方に向けたさまざまなサービスを行っています。不動産売買でお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
●無料査定はこちら
●リハウスAI査定はこちら
※1出典:「減価償却費」の計算について,国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-045/05.htm
(最終確認日:2024年12月23日)


監修者:ファイナンシャル・プランナー 大石泉
株式会社NIE.Eカレッジ代表取締役。CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を保有。住宅情報メディアの企画・編集などを経て独立し、現在ではライフプランやキャリアデザイン、資産形成等の研修や講座、個別コンサルティングを行っている。











