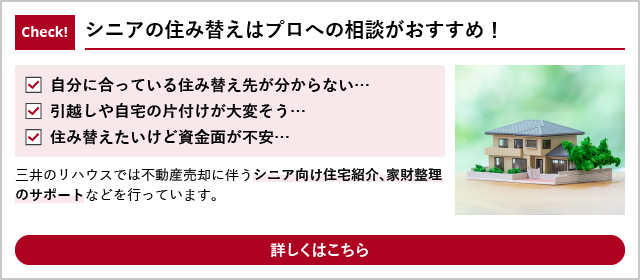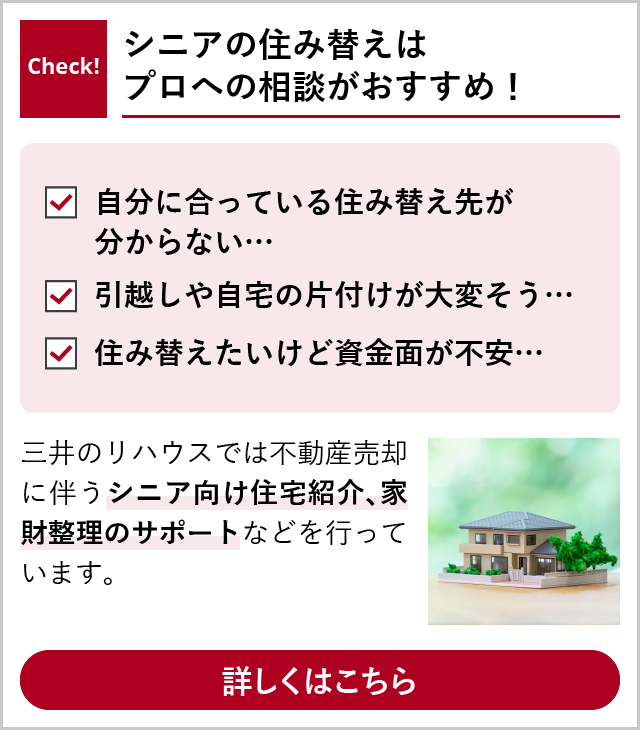サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の費用は?料金相場を解説
「サ高住」と呼ばれるサービス付き高齢者向け住宅は、安否確認と生活相談サービスが提供されるバリアフリー仕様の賃貸住宅で、有料老人ホームより費用を抑えることが可能です。この記事ではサービス付き高齢者向け住宅の特徴や費用、入居条件についてご紹介します。
目次
サービス付き高齢者向け住宅とは
高齢者向け施設のなかには「サービス付き高齢者向け住宅」、通称「サ高住」と呼ばれる賃貸住宅があります。サ高住とは、安否確認サービスやケアの専門家による生活相談を受けられる高齢者専用のバリアフリー賃貸住宅のことです。
サービス付き高齢者向け住宅の運営元は民間事業者で、国の補助金制度が受けられることから施設数が増加しています。そのため、ほかの高齢者向け施設と比べて申し込みから入居までの待機時間が短く、入居しやすくなっています。また、賃貸住宅であるため、これまでと大きく変わらない自由度の高い暮らしを楽しめるでしょう。この記事では、サービス付き高齢者向け住宅でどのような暮らしができるのかに加えて、費用相場なども、ほかの施設と比較しながら解説します。
サービス付き高齢者向け住宅は「一般型」と「介護型」の2種類に分けられます。以下で詳しく見ていきましょう。

一般型
一般型サービス付き高齢者向け住宅は、単身者や夫婦2人暮らしで自立した生活を送っている人、あるいは介護度が低い人に適しています。また、1日のスケジュールが決められていない場合が多く、外出も自由にできるなど、有料老人ホームや介護型サービス付き高齢者向け住宅に比べて自由度が高いという特徴があります。
設備の主な特徴は、居室の広さと住宅内の全てがバリアフリー仕様であることです。個人の居室や共用スペースに段差がなく、トイレや浴室には高齢者に合った高さの手すりが設置されているなど、高齢者が安全に暮らせるように配慮されています。
また、各居室にはキッチン、トイレ、収納設備、洗面設備、浴室などが備えられており、25㎡以上の広さが確保されるように定められています。ただし、共同で利用するキッチンやリビングなどが十分な面積を有している場合には、各居室の広さは25㎡未満(ただし18㎡以上)でも認められます。また、共用部にキッチンや浴室などが設置されている場合には、各居室になくても問題ありません。
一般型のサービス付き高齢者向け住宅では、基本的に介護サービスは提供されていません。そのため、介護が必要になったときには、外部の介護事業所や住宅内に併設された介護事業所と契約することで介護サービスを受けることができます。

介護型
介護型サービス付き高齢者向け住宅は、地方自治体が定める「特定施設入居者生活介護」に指定された施設で、介護度の高い方や認知症の方にも対応しています。特定施設入居者生活介護とは、厚生労働省が定めた基準を満たす施設で受けられる、要介護者を対象とした介護サービスのことです。
介護型ではキッチン、収納設備、浴室を「共用設備」としている場合も多く、一般型と比べると居室の広さは18㎡のところが多いという特徴があります。また、24時間常駐する介護スタッフや日中常駐する看護師から生活支援や身体介護、リハビリ、レクリエーションを受けることができます。

【一覧表あり】サービス付き高齢者向け住宅の費用相場や内訳
サービス付き高齢者向け住宅の費用の内訳とおおまかな目安は以下の通りです。
| サ高住の種類 | 初期費用の目安 | 月額費用の目安 |
|---|---|---|
| 一般型 | 数十万円(家賃2か月~3か月分) | 8万円~20万円 |
| 介護型 | 賃貸方式:数十万円(家賃2か月~3か月分) 利用権方式:数十万円~数千万円 | 10万円~30万円 |
※上表は目安であり、費用の下限・上限を示すものではありません。また、費用は所在地やサービス内容等により異なり、大都市圏は高額になる傾向があります。
初期費用と月額費用について具体的に見ていきましょう。
初期費用
サービス付き高齢者向け住宅は賃貸物件と同様、敷金を払うケースが多く見られます。また、介護型では「利用権方式」という契約形態もあります。一般型と介護型について、それぞれ詳しく確認していきましょう。
一般型
一般型の初期費用の目安は家賃の2か月~3か月分、数十万円程度です。サービス付き高齢者向け住宅は賃貸住宅のため、賃貸借契約の初期費用として、敷金が必要となることがよくあります。
介護型
介護型には、一般型と同様、敷金を支払う賃貸方式と、有料老人ホームと同じ契約形態である利用権方式の2種類があります。利用権方式とは、建物に住む権利と各種サービスを利用する権利が一体化した契約のことです。入居一時金や前払い賃料として数十万円~数千万円が必要になることがあります。
月額費用
サービス付き高齢者向け住宅は賃貸型のため、アパートや賃貸マンションといった一般の賃貸住宅と同様、毎月家賃がかかります。月額費用は、一般型と介護型で異なります。それぞれ見ていきましょう。
一般型
一般型で毎月支払う費用は、家賃、管理費(共益費)、生活支援サービス費です。家賃は近隣の賃貸住宅の家賃相場と相関性があり、月額の目安は8万円~20万円ほどと考えてよいでしょう。そのほか、食費・水道光熱費などが月々かかります。
食事のサービスを受けた場合は、食事をした分だけ支払うケースが一般的です。そのほか、水道光熱費を支払う必要があり、東北や北海道などの寒冷地では、冬場に暖房費として費用が上乗せされるケースもあります。
なお先述の通り、一般型で介護が必要になった場合は、外部の介護サービスを利用するため、介護サービス利用分の費用がかかります。
介護型
介護型の場合、月額の目安は10万円~30万円程度です。この月額費には、家賃・管理費・水道光熱費に加えて、食費・介護保険の自己負担額が含まれます。介護サービス費は要介護度に応じた定額制となり、1割~3割の自己負担となります。

各高齢者施設における費用・相場の比較
高齢者向け施設はサービス付き高齢者向け住宅のほかに、有料老人ホーム、シニア向け分譲マンション、シニア向け賃貸住宅などがあります。これら高齢者向け施設全てに共通しているのは、バリアフリー仕様で高齢者に対応した施設設備となっていることです。
以下で、各高齢者向け施設の初期費用と月額費用を早見表にまとめています。サービス付き高齢者向け住宅とほかの施設を比較・検討している方は、ぜひ参考にしてください。
| 施設 | 初期費用 | 月額利用料 |
|---|---|---|
| サ高住(一般型) | 数十万円 | 8万円~20万円 |
| サ高住(介護型) | 数十万円~数千万円 | 10万円~30万円 |
| 有料老人ホーム | 0円~数千万円 | 10万円~30万円 |
| シニア向け分譲マンション | 数百万円~数億円 | 10万円~15万円 |
| シニア向け賃貸住宅 | 数十万円 | 10万円~20万円 |
※上表は目安であり、費用の下限・上限を示すものではありません。また、費用は所在地やサービス内容等により異なり、大都市圏は高額になる傾向があります。
それぞれの高齢者向け施設の費用や特徴を見ていきましょう。
有料老人ホームとの違い
サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームの主な違いは、契約形態と居室の広さの最低基準です。
| 施設 | 契約形態 | 居室の広さの最低基準 |
|---|---|---|
| サ高住 | 賃貸借契約 | 25㎡(条件付きで18㎡) |
| 有料老人ホーム | 利用権方式 | 13㎡ |
契約形態は、サービス付き高齢者向け住宅では主に賃貸借契約を、有料老人ホームでは主に利用権方式を採用しています。賃貸借契約では、サービスの利用契約を別途結ぶ必要があります。一方で利用権方式の場合、入居者は亡くなるまで施設やサービスを利用できます。また、上記で説明した通り、利用権方式は各種サービスを利用する権利が一体化した契約方式なので、締結するとさまざまなサービスを受けることが可能です。
居室の広さの最低基準は、サービス付き高齢者向け住宅では25㎡以上(条件付きで18㎡)、有料老人ホームでは13㎡以上です。
なお、有料老人ホームには健康型、住宅型、介護付の3種類があり、ホームによって提供されるサービス内容がそれぞれ異なるため、入居前にどのタイプか確認しましょう。それぞれの特徴は以下の通りです。
健康型有料老人ホーム
自立した生活が可能なシニア向けの施設で、施設数は非常に少ないです。食事提供サービスが付いており、介護が必要になった場合は、退去しなければなりません。
住宅型有料老人ホーム
食事や健康管理などの生活支援サービスが提供され、介護が必要になった場合には外部の介護サービスを利用します。
介護付有料老人ホーム
介護サービスの提供が前提とされていて、居住と介護や生活支援などのサービスを合わせて契約します。介護スタッフや看護師が常駐しており、施設内で24時間介護を受けることが可能です。
なお、有料老人ホームの場合、初期費用は0円~数千万円、月額費用は10万円~30万円が目安です。ただし、施設の設備やサポートの充実度、立地や居室の広さなどによって費用が大きく変わることもあるので注意しましょう。

シニア向け分譲マンションとの違い
賃貸借契約や利用権契約となるサービス付き高齢者向け住宅とは異なり、シニア向け分譲マンションは、マンションを購入して所有することになります。そのため、初期費用は高額で、購入後に管理費・修繕積立金や固定資産税などの費用が発生します。
シニア向け分譲マンションは、サービスの規定がないため各事業者によって内容が異なります。食事や洗濯などの日常生活のサポート、入居者の見守りや緊急時の対応といったサービスをオプションで受けられるところが多いです。レストランや美容室など、暮らしに便利な施設が併設されている物件もあります。
施設設備の充実度はサービス付き高齢者向け住宅よりも高い傾向にあり、資産として残せるという大きなメリットがあります。
初期費用はおよそ数百万円~数億円、月額利用料は10万円~15万円です。シニア向け分譲マンションは一般の分譲マンションと比較して設備やサービスが充実している分、管理費や修繕積立金等が高額になる傾向があります。

シニア向け賃貸住宅
シニア向け賃貸住宅とは、シニアが安心して暮らせるように企画・設計された賃貸住宅です。単身者、夫婦を問わず入居は元気なシニアに適しています。
サービス付き高齢者向け住宅との違いは、安否確認や日常生活のサポートといった生活支援の規定がないことです。介護サービスや生活支援が必要になった場合は、入居者自身で外部の介護事業所と契約する必要があります。
シニア向け賃貸住宅の初期費用は数十万円、月額利用料は10万円~20万円が目安です。
●有料老人ホームの費用に関する記事はこちら
●シニア向け賃貸住宅についてはこちら

サービス付き高齢者向け住宅の費用が足りない場合どうする?
サービス付き高齢者向け住宅の価格によっては、年金だけでは賄い切れないことも多いのが現状です。そこで、費用が足りない場合の対応策を以下でご紹介します。
介護サービスに介護保険を使う
介護保険のサービスを利用する際は以下の条件を確認しましょう。
・第1号被保険者(65歳以上):要介護・要支援認定を受けているか
・第2号被保険者(40歳~64歳):医療保険に加入し、16種類の特定疾病に当てはまり要介護・要支援認定を受けているか
上記に当てはまる被保険者は、要介護度に応じてさまざまな介護保険サービスを利用できます。介護サービスは、所得に応じて定められた自己負担額(1割~3割)で利用できるため、介護費用の負担を減らすことが可能です。介護保険制度を利用するには要介護認定を受ける必要があります。詳しくは以下を参考にしてください。
●介護保険制度に関する記事はこちら
●要介護認定の申請方法に関する記事はこちら
持ち家を売却して費用を捻出する
持ち家を売却して費用に充てるのも1つの方法です。サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームに入居するには、まとまった資金が必要です。入居時、持ち家に住む人がいなくなる場合は、持ち家を売却することで資金を作れる場合もあります。
また持ち家を売却すると、家を管理する費用も必要なくなります。入居費用を差し引いても余裕があれば、家の管理費用を老後の生活に充てられるでしょう。三井不動産リアルティのシニアデザイングループでは持ち家を老後生活の資金に活用するご提案もいたします。

サービス付き高齢者向け住宅の費用に関する注意点
サービス付き高齢者向け住宅を検討する際には、いくつか注意点もあるため、以下でご紹介します。
立地によって費用が異なる
サービス付き高齢者向け住宅の家賃は、一般的な賃貸住宅と同様に、立地や築年数によって変動します。駅や都心部に近い場所では家賃が高くなり、築年数が古かったり、駅や都心部から離れたりしていると家賃が低くなる傾向があります。立地や費用など、何を優先したいのかを洗い出してから検討するとよいでしょう。
要介護度と運営体制にずれが生じることもある
一般型のサービス付き高齢者向け住宅の場合、外部事業所と別途契約を行い、介護サービスを受けることが一般的です。暮らしていくうちに入居時と比べて要介護度が高くなり、入居時に契約したサービス内容とずれが生じることもあります。
定期的にサービスの内容と入居者の状態を見直して、このようなずれが起きないようにしましょう。

サービス付き高齢者向け住宅の入居条件とは?
サービス付き高齢者向け住宅に加えて、そのほかの高齢者向け施設の費用をお伝えしました。サービス付き高齢者向け住宅への入居には、連帯保証人・身元引受人が必要なケースが多いという傾向があります。
サービス付き高齢者向け住宅の一般型と介護型では以下のような条件があります。どちらも条件が合えば同居が可能です。入居の条件とともに、同居の条件を以下の一覧表にまとめました。
| 種別 | 居住者の条件 | 同居する人の条件 |
|---|---|---|
| 一般型 | 60歳以上 自立~軽度の要介護者の方 ※要介護認定を受けていれば、60歳未満でも相談可 | ・配偶者(事実上の夫婦と同様の関係にある人も含む) ・60歳以上の親族 ・要支援・要介護認定を受けている親族 ・特別な理由で同居の必要があると知事が認める人 |
| 介護型 | 60歳以上 要介護者の方 ※要介護認定を受けていれば、60歳未満でも相談可 | ・配偶者(事実上の夫婦と同様の関係にある人も含む) ・60歳以上の親族 ・要支援・要介護認定を受けている親族 ・特別な理由で同居の必要があると知事が認める人 |
※上記は一般的な例を述べたもので全ての施設に当てはまるものではありません。
また、一般型は、上記の条件に加えて、以下のような条件を付けていることが一般的です。
・自立した生活ができる(介護保険サービスの利用者も同様)
・認知症ではない
なお、介護型は、介護度の高い方や認知症の方にも対応しています。運営事業者によっては、要支援・要介護認定を受けた方のみを対象としているところもあるので注意しましょう。
サービス付き高齢者向け住宅の特徴を理解して老後の住まいを適切に選ぼう!
サービス付き高齢者向け住宅は、高齢となった夫婦や単身者が抱える生活の不安と、高齢者の入居をためらう賃貸物件のオーナーの状況を受け、2011年に「高齢者住まい法(高齢者の居住安定確保に関する法律)」が改正され、創設されました。
その後、サービス付き高齢者向け住宅は戸数を増やし、2024年10月時点で約28万8,000戸です。現在、高齢者向け施設の供給を促進する施策が各所で行われている最中です。費用は所在地やサービス内容により異なり、大都市圏は高額になる傾向があるため、自分が入居を希望する施設の費用感をあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
一般型サービス付き高齢者向け住宅は自立した高齢者が安全に生活しやすい設備が整っており、外出も自由にできるうえに、自炊もできます。単身者はもちろん、夫婦であっても快適な生活を送れるでしょう。しかし、将来介護が必要になったときのことは想定しておかなければなりません。どの程度の介護状態まで入居できるのか、受けられる介護サービスは何かなどを事前にしっかり確かめておきましょう。
介護型の場合は、介護が必要な高齢者に適切な介護サービスを提供してくれます。それぞれの特徴をよく理解して、自分の暮らしのスタイルや費用、心身の状態に合った住まいを探すことがポイントです。
老後の住まいについて不安に感じることや、ご不明な点がある場合は、三井不動産リアルティのシニアデザイングループに一度ご相談ください。高齢者向け施設のご紹介や老後資金のシミュレーションなど、ご要望に応じてさまざまなサポートをご用意しております。
●三井のリハウスシニアデザインへの各種サポートお問い合わせはこちら
●シニアデザイングループによるお悩み別サポートはこちら


三井不動産株式会社 ケアデザイン室
三井不動産グループが培ってきた住まいと不動産に関する総合力・専門性を生かし、豊かな老後を過ごすためのお手伝いをするとともに、福祉の専門職が豊富な経験に基づいたコンサルティングを通して高齢期のさまざまなお悩みにお応えしています。