
家の相続の流れや費用、手続きの方法など基本情報を解説
家の相続には、複数の手順があり、期限が決まっているものもあります。今回は、家を相続する際の流れを詳しくお伝えします。また、相続手続きにかかる費用や相続した家を使わない場合の対処法についてもご紹介します。
目次
家の相続の流れ
自分や親が家を所有していれば、家の相続はいつか直面する問題といえます。遺産を託す側は、大切な資産を有効に活用してもらうために働きかけておくべきことがあるでしょう。また、相続する側は、遺産相続後にどういった手続きが必要になるのかを知っておかなければなりません。
たとえば親が亡くなって、遺産相続を受けた場合は、亡くなってから10か月以内に相続税を納付する必要があります。相続する資産のなかに建物や土地などの不動産がある場合は、相続税納付までに決めなければならないことや手続きなどの作業が複数発生するでしょう。その際に、段取りが分からないと、スムーズに進められなかったり、親や兄弟とトラブルになったりする恐れがあります。
そこで、今回は、遺産相続のなかでも特に家の相続に焦点を絞って基本的な情報をお伝えしていきます。
まず、家の所有者である被相続人が亡くなってからの家の相続の流れを把握しておきましょう。一般的に家の相続の大まかな流れは以下の通りです。
[ 1 ] 相続人と相続財産を確認
[ 2 ] 遺産分割協議で分け方を決定
[ 3 ] 相続財産の名義を変更
[ 4 ] 相続税の申告・納付
これらの流れに沿って、次項より詳しく解説していきます。
●遺族が行うべき手続きに関する記事はこちら
親が亡くなったらまず何をすればよい?遺族が行うべき手続きTO DOリスト

STEP1 相続人や相続財産を確認する
まず初めに、相続人や相続財産を確認しましょう。ここでは、いくつかの段階に分けてご紹介します。
遺言の有無を確認する
家の所有者である被相続人が亡くなった場合は、まずは、その人が遺言を残しているかどうかを確認しましょう。なぜなら、遺言があるかないかで、相続財産の範囲や割合などが変わってくるためです。ちなみに遺言には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれを順にご紹介します。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言を残す本人が公証人に遺言内容を伝え、それをもとにして2人以上の証人立ち合いのうえ公証人により作成された遺言をいいます。公証人とは、元裁判官や検察官などの法律の専門家で、法務大臣により任命された準国家公務員です。被相続人が亡くなった後に公正証書遺言があるかどうかを確認するには、最寄りの公証役場に行きましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆で書く遺言を指します。なお、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、内容を確認する際には未開封の状態で家庭裁判所に検認の申し立てを行い、検認をしてもらう必要があります。
万が一、誤って遺言書を開封してしまっても、遺言が無効になったり、相続人の資格を失ってしまったりということはありません。しかし、内容を勝手に改ざんしたり、隠したりした場合は、相続人としての権利を失う場合があります。
これまで自筆証書遺言は、遺言書自体が発見されなかったり、誰かが隠してしまったりというケースがあり、被相続人の意思が実現できないことがありました。こういったケースを防ぐために、2020年より自筆証書遺言を法務局で保管できるように法改正が行われています。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、先にお伝えした公正証書遺言と同様に2人以上の証人と公証人立ち合いのもと、本人が作成する遺言です。秘密証書遺言の大きな特徴は、遺言の内容を秘密にしたまま公証役場で証明してもらうことができる点です。
なお、秘密証書遺言を作成するには、手数料として一律1万1,000円がかかるのに加え、遺言の内容が法的に有効でない場合は、無効になってしまうリスクがあります。そのため、秘密証書遺言は公正証書遺言と比較するとあまり用いられない傾向にあります。

相続人を確定する
遺言で特に指定がない場合は、誰が遺産を相続する人(相続人)になるのかを確定させましょう。相続人は、法律で被相続人の配偶者と血縁者と定められており、この法律で定められた相続人を「法定相続人」といいます。
法定相続人を確定する際は、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を利用して確定することができます。
また、法定相続人には、優先順位と割合が決められています。配偶者は必ず法定相続人となり、ほかは決められた優先順位によって相続人が決まります。
相続順位が第1順位となる法定相続人は、子どもです。次いで、第2順位とされる法定相続人は、直系尊属となる親や祖父母で、第3順位の法定相続人は兄弟姉妹となります。相続できる割合については以下の通りです。
| 相続人の構成 | 相続する人 | 相続できる割合 |
|---|---|---|
| 配偶者と子ども | 配偶者 | 2分の1 |
| 子ども | 2分の1 | |
| 配偶者と父母(祖父、祖母) | 配偶者 | 3分の2 |
| 父母(祖父、祖母) | 3分の1 | |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 4分の3 |
| 兄弟姉妹 | 4分の1 |
なお、配偶者がいない場合は、該当の順位にあたる相続人に100%割り当てられます。

遺産を確認する
相続する財産は何があるのか、プラスの財産とマイナスの財産の全てを把握しましょう。主な財産の種類は、以下の通りです。
・不動産
・預貯金や現金
・株式や債権などの有価証券
・ゴルフ会員権
・美術品
・貴金属
・換価価値のあるもの
・借金や貸付
不動産を把握するにあたっては、毎年郵送される固定資産税課税明細書を確認するのが最も簡単です。しかし、山や原野など固定資産税がかからない不動産を持っている場合や、共有の不動産を持っている可能性がある場合は固定資産税課税明細書が送られてきませんので、各市区町村で名寄帳(なよせちょう)の交付を求めて調べる必要があります。
なお、マイナスの財産のほうが多いといった理由で相続をしたくないときは、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」をすることで相続を放棄することもできます。何もしないと相続放棄ができなくなる可能性があるので注意が必要です。
故人の準確定申告を行う
故人の不動産所得があり、確定申告を毎年行っている場合や、給与所得者、年金受給者で申告し還付になる場合は「準確定申告」を行う必要があります。準確定申告とは、被相続人の所得に対して行われる確定申告をいいます。準確定申告は、相続が発生してから4か月以内に申告しなければいけません。通常の確定申告の期間(毎年2月16日~3月15日まで)とは異なりますので注意が必要です。
●不動産相続に関する記事はこちら
不動産を相続する際の流れとは?遺産分割や評価の方法についても解説!
STEP2 遺産分割協議で遺産を分割する
遺言があれば遺言に沿って遺産の分割を行いますが、遺言がない場合や、遺言に記載のない財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行わなければいけません。遺産分割協議とは、相続人で遺産をどう分けるのかを決めることを指します。
遺産分割協議で、法定相続人の全員が合意したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、法定相続人全員の署名と捺印が必要ですので注意しましょう。
万が一、分割方法が分からなかったり、話し合いがまとまらなかったりする場合は、もめごとに発展する場合があります。加えて、財産によっては不動産のように複数人で分けにくいものがあり、手続きが複雑化する場合もあるでしょう。そういった場合は、司法書士や弁護士などのプロに相談するのがよいといえます。
なお、遺産分割協議に決められた期限はありませんが、遺産分割は遅くなればなるほど、処理が難しくなってしまいます。遺産分割がまとまらないと納付する相続税が増える可能性があることや、10年経つと特別受益や寄与分の主張ができなくなるなどの不利益もあります。相続人が死亡したりすると相続人がさらに増えるということもあり得るので、可能な限り早めに遺産分割協議を行うようにしましょう。
●相続に必要な準備に関する記事はこちら
相続の相談は誰にする?必要な準備も含めご紹介!
●遺産手続きに関する記事はこちら
遺産相続手続きを具体的に始めたい!誰にどんな手続きをお願いできる?

STEP3 相続財産の名義を変更する
遺産分割協議の話し合いがまとまり、遺産の分割が決定したら、財産の名義変更を行いましょう。建物や土地などの不動産を相続する場合、建物と土地それぞれの所有者の名義変更が必要です。不動産の名義を被相続人から、相続人である配偶者や子どもへ変更しなければなりません。
万が一、不動産の名義変更をしないでそのままにしておくと、不動産を売却しようと思った際に売却できなかったり、相続関係が複雑化してしまったりといったトラブルの原因になる可能性があります。そのため、名義変更は、相続が発生した際に速やかに行うようにしましょう。
では、名義変更はどのようにして行うのでしょうか?ここからは、相続財産の名義変更を行う際に必要な項目をそれぞれ順にご紹介します。
必要書類を用意する
名義変更を行う際に、必要になる書類がいくつかあります。ここでは、2通りの相続を例に必要書類をご紹介します。
法定相続分で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明
遺産分割協議で決めた割合で相続する場合
・法定相続分で相続をする場合の必要書類
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
書類は、法務局や市町村役場から取り寄せることができます。

法務局で申請する
登記情報は、法務局に登録されているため、相続登記は、法務局で行います。
なお、登記は自分で行えますが手続きが複雑なため、司法書士に依頼して手続きを代行してもらうのが一般的です。司法書士に依頼する際は、名義変更費用のほかに司法書士への報酬が発生しますので、留意しましょう。
名義変更費用を計算する
前述したように、名義変更を行う際には名義変更費用が発生します。ここでは名義変更にかかる諸費用の計算方法をご紹介します。
名義変更の手続きである相続登記を行う際には、「登録免許税」という税金の支払いが必要です。相続時の登録免許税は基本的に「固定資産税評価証明書に記載された不動産の評価額×0.4%」で計算することができます。場合によっては軽減税率が適用されたうえで、具体的な金額が決定します。
STEP4 相続税を申告・納付する
不動産を相続する際に、遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税がかかります。相続税課税の対象となるかどうかは計算で確かめることができます。ここでは、相続税の計算と相続税の申告書について見ていきましょう。
相続税を計算する
相続税は、遺産の総額から基礎控除として定められた額をマイナスした価額に対して課税されます。基礎控除とは、被相続人の遺産のうち一定の金額までは相続税が課税されない(控除される)というもので、その額を基礎控除額といいます。
基礎控除額の計算式は以下の通りです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
この計算式をもとに法定相続人の数と基礎控除額をまとめると以下の通りになります。
| 法定相続人 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
基礎控除額は法定相続人が多いほどその額が多くなります。そのため、法定相続人を把握することは、基礎控除を計算するうえで非常に重要な要素といえるでしょう。
なお、先にお伝えした通り、遺産の総額が基礎控除額を上回る場合は、相続税を申告し納税する必要があります。それは、以下の計算式で確かめることができます。
遺産総額-基礎控除額=課税価格
課税される遺産がある場合には、個人が取得した遺産の割合やそのほかの控除などを踏まえて、個人で支払うべき税額が決定します。具体的な相続税の金額の出し方については以下の記事でご紹介していますのでぜひご覧ください。
●相続税の金額の出し方に関する記事はこちら
相続税の基礎控除とは?計算方法と課税の目安をご紹介!
相続税申告書を作成する
相続税の支払いが必要であれば、申告書の作成を行いましょう。申告書の作成や提出は自分で行うこともできますが、複雑な書類であるため、税理士に依頼するのが一般的です。初めて相続を行う人や、自分で作成することに不安がある人は、プロである税理士に依頼することをおすすめします。

家を所有するとほかにも税金がかかる
ここまで家を相続する流れについてご紹介してきました。ここからは、家を相続し所有した際に発生する費用について詳しく見ていきましょう。先にお伝えした通り、家を相続する際には登録免許税や相続税が発生することがありますが、家を所有した場合、その2つ以外にも税金の支払いが必要になります。支払いが必要となる税金は、固定資産税と不動産取得税です。ここでは、それぞれについてご説明します。
固定資産税
固定資産税とは、家や土地など、固定資産にかかる税金のことで、固定資産の所有者に対して毎年1月1日時点の所有者に対して1年分の固定資産税が課税されます。建物と土地の両方を相続した場合は、それぞれで固定資産税の支払いが必要です。
なお、被相続人が亡くなった年の固定資産税の支払いが残っていて、支払期限に相続登記の完了が間に合わない場合は、相続人のうちの誰かが代表で一時的に立て替えておくほうが得策でしょう。なぜなら、固定資産税を滞納すると延滞金がかかってしまうためです。

不動産取得税
不動産取得税とは、売買や贈与などで不動産を取得した際に課税される税金をいいます。固定資産税とは違い、支払うのは取得した際の1回のみです。基本的に相続によって家を取得した際には、この不動産取得税はかかりません。しかし、以下の条件にあてはまる場合は、課税対象となります。
遺言で法定相続人以外が家を相続した場合
遺言で法定相続人以外の人が家を相続した場合(特定遺贈)は、不動産取得税が発生します。なお、相続の対象が法定相続人の場合は、不動産取得税は課税されません。
贈与によって家を取得した場合
生前に財産を子や孫に贈与する生前贈与によって家を取得した場合は、不動産取得税の課税対象となります。
死因贈与の場合
死因贈与とは、「自分が死んだら、この土地を譲る」というように死亡を原因とする贈与契約を指します。遺言により財産の譲り渡しをする「遺贈」と似ていますが、死因贈与の場合は、贈与する側と受け取る側で契約が必要です。その際、契約書があることが一般的とされています。
上記でご紹介した3つの場合の不動産取得税は固定資産税評価額の3%と定められています。たとえば、評価額が1億円の家を上記の条件で相続した場合の税金は300万円となります。
家を相続しても住まないときはどうする?
上記では相続して家を所有した際のことについて紹介してきました。ここからは、家を相続しても住む予定がなく、空き家になってしまう場合はどうすべきかをご紹介します。
相続後売却する
家を相続した後で売却する方法があります。家は所有するだけで修繕費用や火災保険料などの維持費がかかりますが、家そのものを売却してしまえばそれらの費用はかかりません。また、先にお伝えした通り、家を所有すると固定資産税の支払いが発生しますが、売却してしまえば固定資産税を支払う必要はなくなります。ただし、譲渡によって利益が出た場合には譲渡所得税が発生したり、翌年の住民税や保険料などに影響が出たりすることは覚えておきましょう。
また費用の観点だけではなく、複数人で1つの不動産を相続することになった場合、売却して現金化してしまえば分けやすくなります。
●家の売却を含めて相続の手続きをプロに任せたい人はこちら
相続おまかせ売却パックとは
相続放棄する
家を相続したくない場合は、相続を放棄するという選択肢もあります。被相続人の財産がプラスよりマイナスのほうが多い場合は、相続を拒否することが可能です。相続を放棄した場合は、親が残した借金を返済する必要がなくなります。
なお、相続を放棄する場合は、相続の開始から3か月以内に相続放棄の申し立てを家庭裁判所に行うことが必要です。万が一、この手続きをしなかった場合、債務も含めて全ての財産を相続することになります。
ただし、相続放棄をするとマイナスの財産を引き継がないで済むのと同時に、プラスの財産を相続する権利もなくなる点には、注意が必要です。
相続放棄のほかにも、「限定承認」という方法を選ぶこともできます。限定承認とは、相続によって得た遺産のなかにマイナスの財産がある場合、プラスの財産で支払える範囲内でマイナスの財産を負担するという制度です。限定承認は、債務を考えてもなお所有したい財産がある場合に有効な手段といえるでしょう。
ただし、限定承認は、相続人全員で行わなければなりません。また、「相続財産管理人」を選任する必要があるのに加えて、手続きが複雑なため、限定承認はほかの方法と比較すると手間と時間が必要です。そのため、実際の件数としても限定承認を行う件数は少ない傾向にあります。

遺産相続をスムーズに行うための対策を!
今回ご紹介してきたように、相続では遺産の分割や登記、相続税の申告など、行わなければならないことが山ほどあります。特に、相続財産のなかに不動産がある場合は、必要な手続きが増えるため、時間がかかるといえるでしょう。
まさに相続が発生した場合はもちろん、相続が発生しそうな場合に備えて事前に情報を整理したり、依頼する税理士を探したりして、事前に備えることが重要といえます。
しかし、経験や知識の少ない人が自分だけで作業すると、分からないことや不安なことが出てくるものです。そういったときは、プロのアドバイスを参考にすることをおすすめします。
三井のリハウスでは、相続サポートを行っており、相続の流れや手続きなどの相談が可能です。プロのアドバイスを参考にすることで、相続に対する不安の軽減にもつながるでしょう。まずは、一度相談してみてはいかがでしょうか?

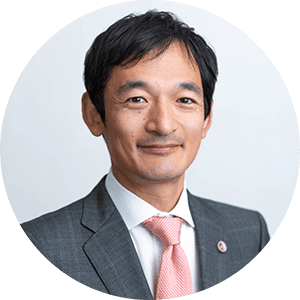
伊藤諭
弁護士法人ASK市役所通り法律事務所代表。弁護士。
地元に根ざした幅広い業務を行い、企業法務や交通事故、相続などを注力分野としている。
多数の講演実績のほか、ネットニュースの監修やメディア出演も行う。
https://www.s-dori-law.com/








