
評価額とは?計算方法や、調べ方、知っておきたい用語を解説!
評価額とは主に税額を計算する際に基準となる不動産の価格です。今回は、地価の種類や、固定資産税・相続税を計算するときに必要な評価額の調べ方について解説します。
不動産の評価額とは?
家の評価額は、通称「不動産評価額」と呼ばれます。不動産評価額とは、土地や建物にかかわるさまざまな税を計算するときに、基準になる不動産の価値を表す価格のことです。
自分の家の価値を知っておくと、不動産売却を検討するときや、税金を支払うときに役立ちます。そこで今回は、家の売買をするとき、税額を調べるときにそれぞれ役立つ評価額について、評価額から税額を求めるシミュレーションを交えながら分かりやすく解説します。自分の目的に合わせて正しい評価額を調べ、役立てましょう!
評価額の種類
不動産の評価額には、大きく分けて以下の5種類があります。
・公示地価
・基準地価
・時価(実勢価格)
・固定資産税評価額
・路線価
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

公示価格
公示価格には公示地価と基準地価の2種類があります。1つずつ見ていきましょう。
公示地価(地価公示価格)
公示地価とは、国土交通省が公表する毎年1月1日時点での土地の価格のことで、地価公示価格とも呼ばれます。都市計画区域(自治体が都市計画法に基づいて指定した地域)内の標準的な土地(標準地)を、2人以上の不動産鑑定士が鑑定して評価を決め、毎年3月に発表されます。
基準地価
基準地価は、公示地価に似ている評価額で、各都道府県が発表する7月1日時点での土地の価格です。公示地価との大きな違いは都市計画区域外の土地も対象に含まれる点です。基準地価の発表は毎年9月と、公示地価の発表と約半年離れているので、お互いの評価額を補正し合う関係といえます。
●公示価格についての詳しい記事はこちら
時価(実勢価格)
公示地価と基準地価は公的機関が評価した土地の価格です。これに対して、実際に市場で売買された価格を示すのが時価(実勢価格)になります。
なお、時価はその取引が行われた時点での価格であるため、現在の市場における需要や景気の動向によって変動します。そのため、あくまで過去の参考価格として見るとよいでしょう。

固定資産税評価額
固定資産税を知りたいときの参考になるのが、固定資産税評価額です。固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳に記載される土地・家屋の評価額のことを指します。また、ほかに都市計画税、不動産取得税、登録免許税の計算にも用いられます。
固定資産税評価額は、総務省が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、各自治体が土地と家屋それぞれに対して決めるものです。なお、木造住宅よりも鉄筋コンクリート造の住宅、一戸建てよりもマンションといったように、建てるコストが高い建物ほど固定資産税評価額は高くなります。
また、家屋の床面積が同じ平米数・同じ構造だったとしても、トイレやシステムバスなどの大きさや数の違いによって固定資産税評価額は異なります。
さらに、固定資産税評価額は築年数によっても変化します。新築家屋と比較して、中古家屋で鉄筋コンクリート造の場合は築20年、木造の場合は築10年で固定資産税評価額は約半分になります。
このように、固定資産税評価額は変化するため、3年に1度「評価替え」といって固定資産税評価額が見直され、納税額が変わる可能性があることを覚えておきましょう。また、評価をするとき、経年劣化の分は減価されて評価額が決定されます。

路線価
土地にかかる相続税や贈与税を知りたいときには、路線価(相続税路線価)を用います。路線価とは、道路に面している土地1㎡あたりの価格で、国土交通省が毎年7月に発表するものです。目安としては、公示価格の80%程度の価格となります。
評価額を自分で調べる方法
各評価額について解説してきましたが、実際にどのような計算方法で評価額を調べるのか知りたい方もいるでしょう。そこで、ここでは公示価格、時価、固定資産税評価額、路線価の調べ方についてご紹介します。
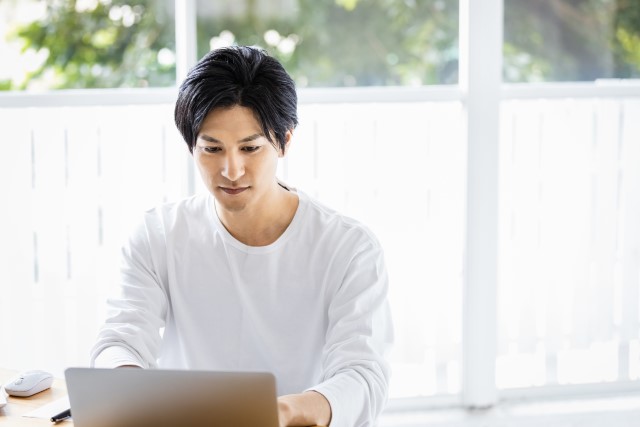
公示価格の調べ方
先ほどご紹介した公示価格は、インターネットで調べられます。国土交通省が運営する「不動産情報ライブラリ」というWebサイトで売却する家に近い土地を検索し、公示価格を調べてみると参考になるでしょう。
●不動産情報ライブラリはこちら
時価の調べ方
時価(実勢価格)は、公示価格と同様に国土交通省による不動産情報ライブラリから閲覧が可能です。具体的には不動産価格情報のメニューから、過去に実際に取引された価格を確認できます。しかし、住所は記載されていないため詳しい物件の特定はできません。そのため所有の土地と条件が似ている、または立地が近い土地を探し、その取引価格を目安にします。ただし、過去の取引なので、あくまで参考程度の数値と認識しましょう。
固定資産税評価額の調べ方
固定資産税評価額は、以下の方法で調べられます。
・課税明細書を閲覧する
・固定資産課税台帳を閲覧する
・固定資産評価証明書を発行する
なお、土地のおおよその固定資産税評価額は公示価格の70%程度、建物についてはその建物を今もう一度建てるのにかかる費用である再建築価格の50~70%程度になります。土地の固定資産税評価額は、公示価格を用いて以下の計算式で算出が可能です。
目安の固定資産税評価額 = 公示価格 × 0.7
●固定資産評価証明書や、入手に必要な書類についてはこちら
路線価の調べ方
路線価を確認するためには、路線価の情報が掲載されたマップである路線価図が必要です。この路線価図は、国税庁のホームページや税務署で確認できます。
また、路線価を用いて評価する方法を路線価方式と呼び、路線価に面積をかけたものが土地の相続税評価額となります。この相続税評価額を基準に相続税や贈与税を算出することが一般的です。なお、相続税の計算には一定の知識が必要なため、税理士といった専門家に依頼することが多いでしょう。

評価額から税額を求めるシミュレーション
ここでは、固定資産税評価額から納税額を求めるシミュレーションをご紹介します。
以下の条件のもと、土地の固定資産税額を計算してみましょう。
・固定資産税評価額:3,000万円
・小規模宅地等の特例:適用
・土地面積:150㎡
まずは課税標準額を求めます。課税標準額とは、評価額に特例や調整が加えられた金額のことです。なお、住戸一戸あたり200㎡までの部分を小規模住宅用地といい、固定資産税の場合、200㎡以下の部分は評価額の6分の1に軽減できます。今回は小規模宅地等の特例が適用されるため、課税標準額は以下の式で求められます。
3,000万円 × 1/6 = 500万円
宅地にかかる固定資産税の標準税率は1.4%のため、
500万円 × 1.4% = 7万円
となり、固定資産税額は7万円であることが分かります。
●固定資産税評価額に関する小規模宅地等の特例について詳しくはこちら
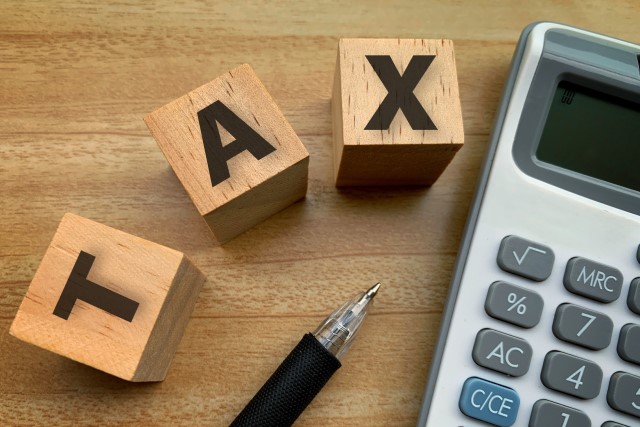
評価額と売値の差
評価額と売値(成約価格)には差異があるのが一般的です。なぜなら評価額は主に税額の基準となるのに対し、売値は不動産売買が成立したときの価格であり、「売主の意向」「買主の希望」「景気」など、さまざまな状況に応じて変化するからです。そのため、売値は評価額より安くなることも高くなることもあります。
また、売却を検討している場合は、不動産会社に訪問査定を依頼することで、自身の不動産の推定成約価格を知ることができます。実績のある不動産会社であれば精度の高い査定額を算出できるため、家の価値についてより詳しく把握できるでしょう。
●無料査定のお申し込みはこちら
●土地売却の相場に関する記事はこちら
評価額や時価を目的に合わせて使い分けよう
これまで、評価額や時価についてお伝えしました。前述の通り、評価額は公的指標から導き出される不動産価値のことであるのに対し、時価は市場の需要と供給のバランスが反映される実際の取引価格のことです。評価額が知りたいのか、時価が知りたいのか、状況に合わせて必要な数値を調べましょう。
売却のために不動産の価値を知りたい場合は、不動産会社による査定がおすすめです。その際、経験や実績の豊富な信頼できる不動産会社を選ぶことで、相場に見合った査定額を算出してもらえるでしょう。
三井のリハウスでは100万件を超える実績に基づいた知見を生かし、精度の高い無料査定を実施しております。また、不動産売却の意志が固まっていない方には、AIが過去の膨大なデータをもとに即時に査定するAI査定もご用意しています。不動産売却をご検討中の方は、まずはお気軽に三井のリハウスまでお問い合わせください。
●三井のリハウスへのご相談はこちら
●無料査定のお申し込みはこちら
●リハウスAI査定はこちら
●家の売却方法に関する記事はこちら


宮原裕徳
株式会社ラムチップ・パートナーズ 所長。税理士。日本のみならず、東南アジアも含めた不動産にかかわる会計・税務に精通している。法人や個人向けに節税セミナーなども行っている。
https://www.miyatax.com/













