
亡くなった親の家を兄弟で売却する4つの方法!相続した不動産の売り方を解説
亡くなった親の家を相続する際、兄弟間でトラブルが起きることも珍しくありません。トラブルを避けるためには、分割や売却の手順について、兄弟間で話し合うことが重要です。この記事では、相続登記した親の家を売る方法について詳しく解説します。
目次
亡くなった親の家を兄弟で売るときの注意点
亡くなった親の家を売却する際、兄弟間の話し合いがうまくまとまらないと、トラブルに発展する恐れがあります。たとえば、遺産分割協議でどのような方法をとるか、親の家を売却して得た代金をどのように分けるかなどで対立することが考えられるでしょう。
亡くなった親の家を相続しないままの売却はできず、売却するには相続登記が必要です。亡くなった親が所有していた不動産を兄弟で売りたい場合、相続登記により亡くなった被相続人から相続人へ名義変更がされているか否かについて注意しましょう。
●相続登記に関する詳しい記事はこちら
●不動産を相続する方法に関する詳しい記事はこちら
亡くなった親の家を兄弟で相続する場合、遺産分割を行う必要があり、不動産の名義が単独名義となるケースもあれば、共有名義となるケースもあります。特に、共有名義で分割した場合、売却の方法は複数になるため注意しましょう。詳しくは後ほど説明します。

亡くなった親の家を兄弟で相続するための遺産分割の方法
親が亡くなって相続が発生した場合、兄弟で実家を売却する前に、名義変更のための遺産分割方法を決めます。亡くなった親の家を売るための主な遺産分割方法は、以下の4種類です。
・現物分割
・換価分割
・代償分割
・共有分割
いずれかの遺産分割方法を選び、相続登記を行った後に売却ができます。
現物分割
現物分割とは、それぞれの相続人が相続財産を種類別に現物の状態で相続する遺産分割のことです。この方法のもとでは、兄弟間で不動産は兄、株式は弟が承継するといった遺産の分割がなされます。現物分割後は、兄弟のなかで家を単独で承継した1人だけが売却を行えます。
なお、土地に関しては、分筆により兄弟で分割して相続することが可能です。分筆によって得た持分は、持ち主が自由に売却できます。
換価分割
換価分割とは、登記後に亡くなった親の家を売却し、その代金を相続人である兄弟間で分け合う方法です。この方法を用いることで、売却を済ませながら現物分割より公平に遺産を分割できます。兄弟で行う場合、換価分割を目的とした代表者を1人決めて不動産の売却を行い、ほかの兄弟へ必要な額を分ける形になるでしょう。ただし、不動産売却の際、相場を知らずに売り出し価格を設定したり、焦って売り急いだりすると、安値で売って損をしてしまう恐れがあります。売却の際には慎重に売却活動を行いましょう。
●不動産売却のご相談はこちら
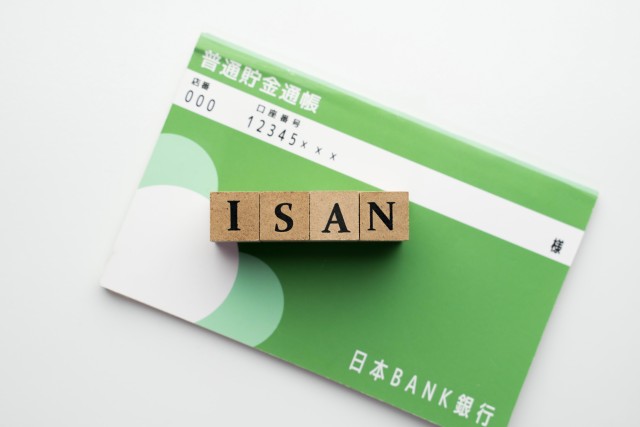
代償分割
代償分割とは、相続人のうちの1人が不動産全体を相続し、ほかの相続人に代償金を支払う遺産分割方法です。この方法であれば、ほかの兄弟に代償金を支払う必要はありますが、兄弟の1人が亡くなった親の家を単独で相続して売却することが可能です。また、換価分割と異なり、代償金を支払えば売却を急がなくてよいため、遺産分割後、売却するまでは亡くなった親の家にそのまま住んでいられます。
共有分割
共有分割は、不動産を兄弟で共有して相続する方法です。この方法では、相続人へ名義変更する際に兄弟の共有名義となります。売却の際は、単独名義の不動産と異なりいくつかのパターンがあるため、しっかりと理解したうえで最適な方法を選びましょう。共有分割で相続した不動産の売却方法は、次の章で詳しく説明します。
●売却による分割方法に関する詳しい記事はこちら

亡くなった親の家を兄弟の共有分割で相続した際の売却方法4つ
亡くなった親の家を兄弟で共有分割して相続登記をした場合は、名義人が複数人となるため、売却にはいくつかのパターンがあります。主な売却パターンは以下の4つです。
・共有者全員の同意により、不動産全体を売却する
・自分の共有持分だけを売却する
・ほかの共有者に自分の共有持分を売却する
・ほかの共有持分を全て買い取った後に売却する
それぞれについて以下で詳しく解説します。
●不動産共有名義に関する詳しい記事はこちら
共有者全員の同意により、不動産全体を売却する
共有者の全員が同意すれば、不動産全体を相場価格で売却することが可能です。この場合、兄弟全員が名義人として売主になり、売買契約を結んで決済を行います。売却によって得られた代金を兄弟で分割すれば、亡くなった親の遺産を持分割合に応じて分配できます。兄弟間の意見の衝突なしに売買活動を進められる場合には効果的な方法だといえるでしょう。

自分の共有持分だけを売却する
共有名義の不動産でも、専門の不動産買取業者に自分の持分だけを売却することが可能です。自分の持分を業者に買い取ってもらうことで、代金を受け取りながら、亡くなった親の家の共有関係から脱することができます。ただし、買取の場合は、市場での売却に比べて得られる代金が安くなりやすいうえに、第三者と共有することが人間関係や訴訟のトラブルを招きやすいため、注意が必要です。
ほかの共有者に自分の共有持分を売却する
家の共有者であるほかの兄弟に、自分の持分を買い取ってもらうことも可能です。ほかの兄弟に経済的余裕があったり、より大きな持分を欲しがっていたりする場合にはこの方法を検討してみるとよいでしょう。兄弟間であれば比較的スムーズに売却しやすいため、有効な手段といえます。
ほかの共有持分を全て買い取った後に売却する
ほかの兄弟から共有持分を全て買い取り、親の家を共有名義から単独名義にして売却する方法もあります。兄弟が親の家の共有持分を手放したがっていたり、ほかの共有持分を買い取れる資金力があったりする場合は、この方法で売却を検討してみましょう。
亡くなった親の家を兄弟で売る際のトラブル2つ
遺産分割協議や共有持分の売却の際に、兄弟間で起こり得るトラブルやその対策について解説します。
遺産分割協議のときに対立が起こる
亡くなった親の家を売却したい場合は、遺産分割協議において、売却する意向と分割方法を兄弟で合意することが必要です。そもそも家を残すか売るかで意見が分かれ、兄弟間で対立が起きてしまうこともあるでしょう。そのような場合は、代償分割を選択することで家を残したい兄弟の1人が家を相続し、売却を保留にできます。ただし、代償金の金額を遺産分割協議で話し合って決定しなくてはなりません。また、口約束によって後にトラブルに発展しないよう、話し合いで決まった内容は遺産分割協議書に残しておくようにしましょう。
それぞれの分割方法について兄弟で確認しつつ、亡くなった親の家をどのような分割方法で、誰の名義で相続するかをよく話し合うことが大切です。
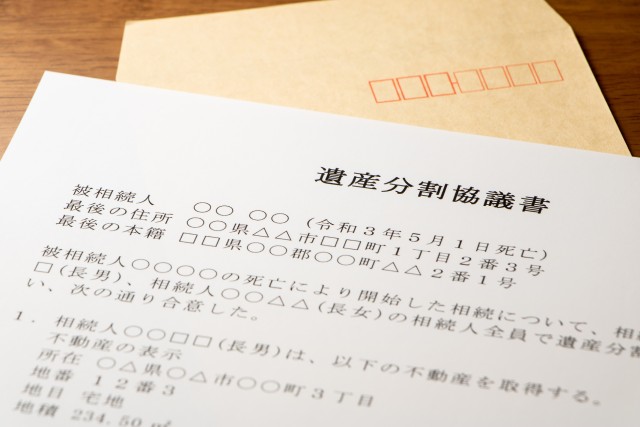
共有持分を売却するときに対立が起こる
ほかの共有者に自身の共有持分を買い取ってもらう場合、その売買の成約価格についてトラブルになる可能性があります。成約価格は査定や不動産鑑定で提示された価格を参考に、お互いが納得できるよう話し合って決めましょう。
また、共有持分を売却する際には、登記費用や印紙税などがかかる点に注意が必要です。
自分の共有持分のみを売る場合でも、トラブルや兄弟との関係悪化を避けるために、事前に相談・確認をしてから売却するようにしましょう。
●共有持分の売却で起こるトラブルや費用に関する詳しい記事はこちら
●相続した不動産を売却して分割する際の税金に関する詳しい記事はこちら
親の家を相続して売却する流れ
亡くなった親の家の相続手続きと、売却の流れは以下の通りです。
1.遺言書の確認
2.相続人の確認
3.遺産分割協議(遺言書がない場合)
4.相続登記
5.査定・売却活動
6.売買契約
7.決済・引渡し
相続では、多くの手続きや書類が必要です。遺産分割協議の際や、共同で不動産売却を行う際は、兄弟でよく話し合って決めるようにしましょう。
●遺産相続手続きに関する詳しい記事はこちら

亡くなった親の家を売る際は査定を活用しよう
亡くなった親の家を兄弟で売りたい場合、遺産相続協議や共有持分の売却に関する場面では、兄弟間での相談が非常に重要です。兄弟での話し合いを経て売却の準備が整ったら、スムーズに家を売るために不動産会社に査定を依頼しましょう。
三井のリハウスでは、豊富な取引実績を生かして不動産の売却活動をサポートします。無料査定も行っているため、相続した不動産や共有名義の不動産の売却にお困りの方は、ぜひ三井のリハウスにご相談ください。
●無料査定はこちら


監修者:ファイナンシャル・プランナー 大石泉
株式会社NIE.Eカレッジ代表取締役。CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を保有。住宅情報メディアの企画・編集などを経て独立し、現在ではライフプランやキャリアデザイン、資産形成等の研修や講座、個別コンサルティングを行っている。










