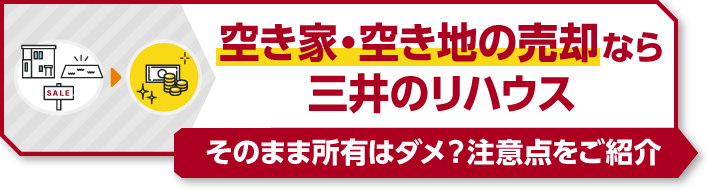田舎の家を売却したい!売却方法やポイントを解説
田舎の家は、需要の低さや築年数の問題で売却しづらいことがあります。しかし、ポイントを押さえて工夫をすれば売却しやすくなることもあります。今回は、田舎の家を売るための工夫や注意点をご紹介します。
田舎の家が売却しづらい理由
少子化による人口減少や高齢単身世帯の増加に伴い増え続け、社会問題にもなっている空き家。過疎化が進む地方では特に深刻な問題となっています。空き家は持っているだけで管理費用や固定資産税などの経済的負担がかかります。また、空き家は周辺環境に悪影響を及ぼし、近隣住民とのトラブルになる可能性もあるため、放置せずに処理をしたほうがよいでしょう。
使用せず経済的な負担ばかりかかるような家は売却したいところ。しかし、田舎の家は売却しづらいのが現状です。そこで今回は、田舎の家を売却するための方法やできるだけ高く売却するためのポイントなどをご紹介します。
まず、なぜ田舎の家は売りづらいのでしょうか?田舎の家が売却しづらい要因は、田舎の家ならではの特徴的な2つの理由と、一般的な理由があります。まずは田舎の家特有の理由から見ていきましょう。

需要が少ない
田舎の家を売却しようとしても、もともと周辺の人口が少ないことやそこに家がほしい理由が少ないことが要因で、家を購入したいという需要があまり期待できません。地方では、既にある実家で親と同居している、あるいは親から相続した一軒家に住み続けることが多く、なかなか新たに家を購入しようというニーズが生まれづらいのです。
また、都心部から地方へ移住する人の数はまだまだ限られているので、家のニーズとしては賃貸、売買とも少ないといえるでしょう。
対応してくれる不動産会社が見付けにくい
そもそも、地域によっては、不動産会社の営業エリアから外れてしまい、売却を依頼できる不動産会社がなかなか見つからないことがあります。不動産会社も企業である以上、コストと利益のバランスを考えて活動をしています。そのため、対応する(できる)営業エリアというものがあり、物件がこのエリアから外れてしまうと、その会社では売却の媒介(仲介)を引き受けてもらえないことがあります。特に田舎となれば、営業エリアから外れる可能性が高くなり、売却の依頼先を見付けることが一苦労です。
次に、田舎の家に限らず、家が売却しにくくなる場合の理由を見ていきましょう。
築年が古い
たとえば、親や親戚から相続した物件では、建物の築年が古く、建物や設備の老朽化が進んでいる傾向があります。特に築年の古い物件では、安全性と物件としての魅力という2つの観点から売れにくくなります。
物件によっては、1981年6月以降に適用された新耐震基準を満たしていない建物もあり、耐震の面で安全性に課題がある場合があります。また、外観が古かったり、機能的にも古く使いにくい場合、その物件に住みたいと思わないことが多くなりますよね。
維持費がかかる
一般的に築年が相当に古くなった物件の特徴として、買う側からすると物件価格が安くても修繕費や維持費が高く付くことが多く、購入を躊躇してしまう傾向があります。建物は時間の経過とともに老朽化していくもの。古くなった建物では、状態の悪い箇所の修繕費がかかることが予想されます。
家の購入を検討している人にとって、建物の維持費も重要な判断ポイントとなります。売り出し価格を安くしても、維持費が多くかかるような物件だと売却が難しくなるのです。

田舎の家を売却する方法
田舎の家を売却するにはまず、その地域の物件の売買を得意とする不動産会社を探すことが売却を成功させる第一歩です。その地域の物件の売却実績が豊富な不動産会社を探し、扱いに困っている物件の対処法を、その会社に相談してみるとよいでしょう。その地域の物件の扱いに強みを持つ不動産会社だからこそ分かる活用方法を提案してくれることがありますよ。
頼れる不動産会社を見付けることを前提として、そのままでは売りづらい田舎の家を売却するためにはどんな方法があるでしょうか?ここでは、2つの対策方法をご紹介します。
売却前にリフォームやリノベーションを行う
田舎の家を売却するための方法として、リフォームやリノベーションを検討しましょう。不動産を売却する際、物件の見た目から受ける印象は重要です。床・壁の張り替え、外壁や屋根のふき替えや塗装、窓やドアの修理など必要最低限のリフォームで第一印象をアップさせることができますよ。
リフォームやリノベーションは住まいの防犯性や安全性を高めることにもつながります。たとえば、鍵を新しいものに交換することで、窃盗や空き巣の被害が発生するリスクを抑えることができますよ。
ただし、過度なリフォームやリノベーションは控えるほうがよいでしょう。リフォームにかけた費用以上に高く売却できるとは限らないため、売却するうえで必要最低限のリフォームに留めることがポイントになります。
更地にしてから売りに出す
建物が古く、リフォームやリノベーションに相当の費用がかかるけれど現在のままでは売却が難しい場合、建物を解体し、更地にしてから売りに出すというのも1つの方法です。
更地であれば、土地購入者が自分の好きなように土地を利用できるため、需要の幅が広がり、古い建物があるよりは売りやすくなります。もし、地域的に居住用の住宅としての利用が難しい場合、セカンドハウスや資材置き場としての利用、土地が相当に広ければ、太陽光発電所用地として活用することも考えられます。
また、売主があらかじめ更地にすることで、買主は解体費を負担することないため、売りやすくなるという側面もあります。なお、解体費用については、解体する建物の立地状況や建物の構造(RC造やS造、木造など)・規模(階数)、面積、築年数によっても金額が異なってきます。
たとえば、数百万円かけてリフォームやリノベーションを行っても、その費用以上の価格で売却できるとは限りません。したがって、リフォームやリノベーションを行うのがよいか、家を解体して土地売却するのがよいか、売却を検討する段階で比較検討するようにしましょう。
●空き家売却に関する記事はこちら
空き家を売却するには?コストを抑えてスムーズに処分する方法

田舎の家を売るときの注意点
家を現在のまま売りに出すか、リフォームやリノベーションを行ってから売りに出すのか。はたまた、建物を解体して更地として売りに出すのか。どの選択をとるにせよ、田舎の家を売却する際は以下の2点に注意が必要です。
住宅に住まなくなってから3年以内に売却する
現在空き家となっている家の売却を検討しているのなら、その家に住まなくなった日から3年が経つ年の年末までに売却するようにしましょう。
そもそも家を売却して利益が出ると、その利益に対して税金が課税されます。この家(不動産)の売却で発生した利益のことを、「譲渡所得」といい、譲渡所得には所得税や住民税がかかるのです。
ただし、いくつかの条件を満たせば、売却時の譲渡所得から最高3000万円まで控除ができる特例が利用できます。この特例を、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」といいます。この特例を受けるための条件の1つが売る家に住まなくなって3年以内で売却することです。
また、建物を解体した場合は、次の2つの条件も満たす必要があります。
・その敷地の譲渡契約が建物を解体した日から1年以内に締結され、かつ、解体した建物(住宅)に住まなくなった日から3年が経つ年の年末までに売却する
・建物を解体した日から譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などとして利用していない
なお、この特例を受けるための必要書類の1つに、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]というものがあります。確定申告書に譲渡所得の内訳書を添えて提出しましょう。また、建物を解体した場合には、解体証明や建物滅失登記(登記事項証明書)などの添付も必要になります。
●譲渡所得に関する記事はこちら
不動産譲渡にかかる税金とは?「譲渡所得税」の基礎知識

物件の管理
物件の売り出し中はもとより、いずれ売りに出すことを検討しているのならば、建物や土地の管理にも配慮が必要です。その住宅に住んでいる、あるいは定期的に利用しているなら、人の出入りで必然的に建物内の換気がなされ、多少の手入れは行われるものです。しかし、空き家となっている場合は、建物が急激に傷んでしまうため、建物や土地の管理に注意が必要です。空き家であっても、それほど築年数が古くなければ、管理を徹底することで、買い手が付きやすくなります。
また、空き家の場合、管理せずに放置しておくと、ゴミの違法投棄や犯罪の拠点になってしまうこともあり、近隣からの苦情に発展してしまいます。さらに、放置期間が長く、管理状態が悪いと、自治体から特定空き家として認定される場合があります。
この特定空き家に認定されると、通常土地の上に建物があると受けられる固定資産税の優遇がなくなり、更地と同じ税金が課せられます。通常の建物がある場合よりも割高な税金の支払いが発生することになるのです。
なお、空き家の管理については、自分や家族で定期的に訪れて管理することもできますが、最近では空き家の管理を専門に行う業者への委託を検討してもよいかもしれません。
売却時にアピールできるポイント
不動産の売却では、できるだけスムーズに、少しでも高く売却したいものですよね。先ほど説明したように売却しづらい田舎の家ですが、田舎の家だからこその魅力もあります。納得できる売却の可能性を高めるため、売却時にアピールできるポイントを3つお伝えします。
豊かな自然環境でのびのび暮らせる
郊外や田舎への住み替えを目的で物件を探している人のなかには、「老後は家庭菜園を楽しみつつ静かに暮らしたい」「子育てや病気療養のために自然豊かなところでのびのびと暮らしたい」「緑に囲まれた暮らしに憧れている」などといった理由から、静かで自然豊かな周辺環境に重きを置いている人もいます。豊かな自然や澄んだ空気など、その土地ならではのアピールポイントがあれば、売却の可能性が高まるでしょう。
敷地や建物にゆとりがある
田舎の土地は都会と比べて安く、広い土地に建つ家も多いため、安い価格でより広い家に住むことが可能です。家が広ければ、書斎、趣味専用の部屋、仕事部屋など、部屋割りにもゆとりを持った家に住むこともできますね。
働き方改革や感染症の拡大防止のためにリモートワークが普及し、住まい選びの基準が変わりつつあります。在宅勤務も可能な環境を確保できることは、さらにリモートワークが普及して来ると家選びの重要なポイントになります。
税金が安い
郊外や田舎は固定資産税が安いところもまた、ポイントの1つです。毎年納付する必要がある固定資産税が安ければ、長い目でみると大きな差になりますね。
土地や建物にかかる固定資産税は、所有する固定資産の評価額に標準課税率を掛けて算出します。税率は自治体によって異なりますが、1.4%が標準です。
固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額) × 税率
ちなみに固定資産評価額とは、土地や建物の価値をどう評価するかを定めた「固定資産評価基準」に基づいて、自治体ごとに決める評価額のことです。そもそも土地の固定資産税評価額が都心部と比べて安い田舎の土地の固定資産税は安くなってきます。
●固定資産税評価額に関する記事はこちら
固定資産税評価額とは?自分ですぐできる税金の計算方法

売れない場合は買い取りという選択肢も
上記のような田舎の物件ならではの魅力があるとはいえ、需要が限られた田舎での不動産売却は思い通りに進まないことも十分考えられます。どうしても売れない場合は、不動産会社に買い取りしてもらえるか相談してみましょう。
不動産会社に買い取ってもらうメリットは、速やかに現金化できるところです。通常の仲介による売却では、不動産会社と媒介契約を結んで売却活動を行い、購入希望者の内覧、価格などの交渉を経て、買主と売買契約を結びます。以上の手順を踏んで売買契約を結んだ後にも買主のローン審査などもあり、一般的に売却完了までに3か月から半年程度かかります。
それに対して不動産会社の買い取りであれば、早ければ1か月程度で取引が完了します。
買い取りの場合、不動産の査定後、その金額で納得できれば、売買契約を結び早ければその後1か月以内に決済・引渡しとなります。
ただし、買い取りでは一般的に仲介売却の6~8割程度の売却価格となる点に注意が必要です。売却価格が安くなるのは、リノベーションにかかる費用が不動産会社負担となるからです。買い取りの査定額は、不動産会社が物件を買い取りした後、買い取った不動産を活用するために必要な費用や会社としての利益分が、あらかじめ差し引かれた額なのです。
なお、当然ながら買い取りする物件は売れる見込みのある物件のみとなるので、田舎の家なら、買い取りしてもらえる物件は特に売却できそうな物件に限られます。しかも、前述のように営業エリアなどの条件もあるので、検討する前に確認しておくとよいでしょう。
空き家は、売却せずにいると、いつまでも固定資産税やメンテナンス代がかかり続けることになります。 今後かかる時間や費用、手間を考慮して、1番適切な売却方法を判断するようにしましょう!



秋津智幸
不動産サポートオフィス 代表コンサルタント。公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士。物件の選び方や資金のことなど、不動産に関する多岐のサポートを行なう。