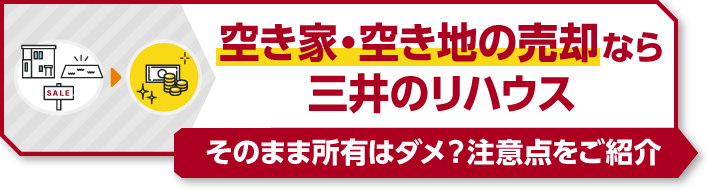実家の空き家はなぜ売れない?理由と解決策を解説
親の死後、空き家になった実家がなかなか売れずに困っている人もいるのではないでしょうか?この記事では、大きな社会問題にもなっている空き家を売る方法や、売却できない場合の処分方法、また今からできる対策について紹介します。
目次
実家の空き家が売れない理由
親の死後、空き家になった実家を売却したいのに、なかなか売れないとストレスを感じるものでしょう。なぜ実家の空き家が売れないのか、主な理由について解説します。

立地が悪い
不動産を購入する際、多くの人が気にするのは利便性です。実家が地方や田舎の不便な場所にある場合、都市部に比べて不動産の流通が少ないため、買い手を見つけるのが困難になります。
建物の老朽化が激しい
一般的に、築年数が古くなればなるほど建物の資産価値は下がるとされています。建物の耐用年数を考えると、木造であれば22年、鉄筋コンクリート造であれば47年経過していると価値(税法上の価値)はゼロと見なされるのです。税法上の価値がゼロになっても住めるので売れないわけではありませんが、売れたとしても好条件で売るのは難しいケースが多いでしょう。
実家の空き家が売れないときの解決策
ここからは、実家の空き家がなかなか売れない場合の対策について紹介します。

[ 1 ] 売り出し価格を見直す
公益財団法人東日本不動産流通機構の「首都圏不動産流通市場の動向(2023年)」※1によると、2023年の首都圏における中古戸建住宅の売り出し価格(新規登録物件の価格)は4,294万円、成約価格(実際に売買が決まった価格)は3,848万円と差があります。さらに過去10年間、売り出し価格と成約価格に差がある傾向に変化はありません。つまり、今の価格で売れない場合、値下げすると売れる可能性が高くなります。
[ 2 ] 「古家付き土地」として売る
実家の空き家の需要が見込めないときは、土地のみの価格で売る「古家(ふるや)付き土地」として売却する方法があります。売り出し価格は安くなってしまいますが、売主は解体費用を負担しなくて済むうえ、中古住宅として売るよりは買い手が付きやすいというメリットがあります。
[ 3 ] 更地にして売る
建物の老朽化が激しい場合は、解体して更地にすると売れやすくなります。ただし、建物を壊すと、固定資産税の軽減(住宅用地の特例)が適用されなくなり、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」についても適用外となる可能性があるので、慎重に検討しましょう。
●固定資産税の住宅用地特例についてはこちら
●被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例についてはこちら
[ 4 ] 買取業者に依頼する
空き家を早く手放したい人や、現金化を急いでいる人は、買取業者に直接買い取ってもらう方法があります。ただし、買取価格は仲介で売却する場合の約6~8割の価格になってしまう点には注意しましょう。
[ 5 ] 不動産会社を見直す
売り出し価格や建物に問題がないのに売れない場合は、不動産会社や媒介契約の種類を見直してみましょう。通常、不動産の売却が完了するまでには3~6か月程度かかるとされています。6か月経過しても進展がない場合には、不動産会社や媒介契約の変更を検討するのがおすすめです。
●空き家を手放す方法について詳しくはこちら
空き家の実家を処分したいとき
実家の空き家がどうしても売れないときは、処分するという選択肢もあります。空き家を放置している間も固定資産税はかかり続けるため、処分方法を検討しましょう。空き家バンクや、国に引き取ってもらう制度を利用して処分するケースが一般的です。詳しくは以下の記事でご確認ください。
●実家が売れない場合の手段について詳しくはこちら
ほかには、自治体や法人に寄付する方法もあります。ただし、該当の自治体や法人にとって利用価値のある物件でないと受け付けてもらえないため、寄付が成立しないことも多いでしょう。また、寄付できる場合も、高い確率で建物は取り壊して更地の状態にすることが求められます。まずは、自治体のホームページなどで、寄付を受け付けているかどうかチェックしてみましょう。

空き家を処分する際に活用できる補助金制度
空き家を処分する際に、自治体によっては補助金を支給してもらえます。空き家は老朽化による倒壊の危険性や景観、衛生、治安などの観点から、地域住民の生活に影響を及ぼす恐れがあるとされており、自治体は積極的に解体または建て替えを進めたいと考えているためです。
2015年には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、特定の空き家を適正に管理しない所有者に対して、市町村は行政指導や、場合によっては命令を下すことが可能になりました。この命令に背くと罰金が科されたり、行政が代わりに解体を実施して、その費用を請求されたりするケースがあります。
一方で空き家の解体費用は、広さや造りによって異なりますが、70万~300万円程度と安価ではないため、処分したくてもできない所有者もいるでしょう。ここからは、空き家処分に関する代表的な補助金制度を紹介します。
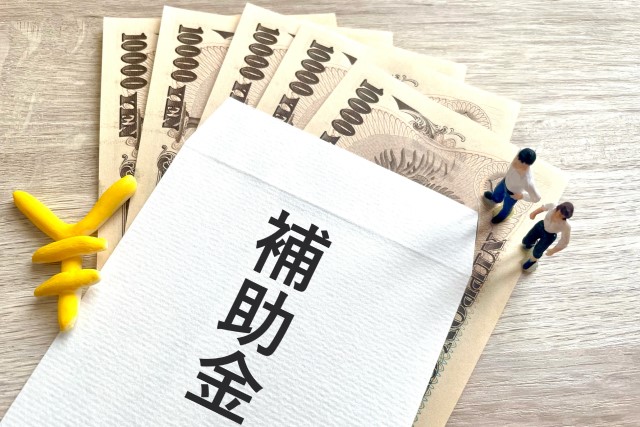
老朽危険家屋解体撤去補助金
老朽危険家屋解体撤去補助金とは、老朽化による倒壊の可能性が高い家屋の解体に利用できる制度です。支給額は自治体によって異なりますが、解体費用の2~5割程度が支給されます。なお、自治体の認定や耐震診断を受けないと、補助金を受給できないため注意しましょう。
都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金
都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金とは、都市の景観を守るために、建物を解体した場合、補助金が支給される制度のことです。こちらの制度の適用を受けるためには、解体工事後の土地利用について、都市の景観形成基準を満たす必要があります。支給額は自治体ごとに異なりますが、解体費用の2~5割程度とされています。
建て替え建設費補助金
建て替え建築費補助金は、老朽化した家屋を解体して住宅を新築する際に、一定の基準を満たすことで解体費用や建築費用が補助される制度です。支給額や条件は自治体によって異なるため、自治体に確認を取りましょう。
今からやっておきたい実家の空き家対策
2020年に発表された国の調査によると、空き家の取得経緯の約55%が相続※2であることが分かっています。実家を相続する前に準備を進めて、納得いく売却につなげましょう。

相続について家族で話し合う
実家が遠方だったり、兄弟が離れた場所に住んでいたりする場合には、親の死後、短い時間で実家の相続について話し合うのは難しいでしょう。また、遺言書に実家を守るよう書かれていたり、兄弟間で意見が割れたりすると、実家を売却できず空き家のまま放置してしまうということにもなりかねません。所有者が存命のうちに、相続人全員で、実家が空き家にならないためにはどうすべきか計画を練っておくことが大切です。
実家の査定をする
相続した実家を売ることになったとき、どのくらいの資産価値があるのか把握することが重要です。実家の売却前には、不動産会社に査定を依頼しましょう。実績のある会社に依頼すれば、精度の高い査定結果が得られる可能性があります。
三井のリハウスでは、所在地や築年数、面積、間取りなどの物件情報や、類似物件の取引価格などをもとにした簡易査定や、実際に物件を訪問し、立地や建物の状態などを詳細にチェックする訪問査定を無料で行っています。お気軽にお問い合わせください。
相続税にいくらかかるか計算する
不動産を相続する際、予想外に大きな出費となりがちなのが、土地にかかる相続税です。実家の相続時に、相続税がかかるのか、かかるとしたらどれくらいかを計算しておくと慌てずに済みます。
●相続税のシミュレーションはこちら
不動産の相続・売却はプロに任せるのがおすすめ
不動産の相続は手続きが複雑なため、慣れていない場合は、費用はかかりますが税理士や司法書士といったプロに任せるのがおすすめです。三井のリハウスでも、遺産分割協議書の作成や相続税の申告サポート、不動産売却、家財整理など、面倒な相続の手続きと不動産売却を合わせてトータルサポートしています。実家の相続や売却でお悩みの方は、一度お問い合わせください。
●相続お任せ売却パックについてはこちら

実家の売れない空き家は放置せず今すぐ売却
空き家となった実家を所有したままでは、管理する手間や移動のための交通費、固定資産税など、大きな負担を強いられるでしょう。使う予定がないならできるだけ速やかに売却することがおすすめです。三井のリハウスは累積取扱件数100万件以上の実績や、業界最大級のネットワークを生かした不動産査定を行っています。査定だけでなく、不動産に関するあらゆる相談を承っておりますので、実家の空き家が売れずにお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
●無料査定のお申し込みはこちら
●不動産売却についてのご相談はこちら
※1出典:首都圏不動産流通市場の動向(2023年),公益財団法人東日本不動産流通機構
http://www.reins.or.jp/
(最終確認:2024年4月30日)
※2出典:令和元年空き家所有者実態調査報告書, 国土交通省 住宅局
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001377049.pdf
(最終確認:2024年4月30日)


監修者:ファイナンシャル・プランナー 大石泉
株式会社NIE.Eカレッジ代表取締役。CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を保有。住宅情報メディアの企画・編集などを経て独立し、現在ではライフプランやキャリアデザイン、資産形成等の研修や講座、個別コンサルティングを行っている。
https://www.izumi-ohishi.co.jp/profile.html