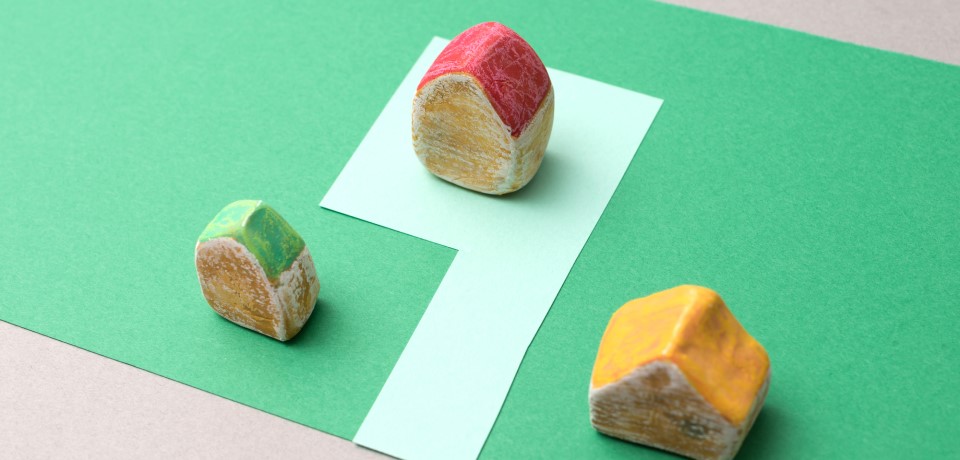
旗竿地が売れないと言われる理由4つ!後悔しない売却のコツも解説
旗竿地は、一般的に売れにくいと言われています。しかし、工夫をすることで売れにくい旗竿地も売却が可能です。今回の記事では、売れやすくするポイントや注意点、土地の評価を調べる方法を詳しく解説します。
目次
旗竿地とは
旗竿地(はたざおち)とは、道路から家につながる路地の部分が細い「竿」の形になっており、そこから奥に広がる「旗」の部分が建物を建てるための敷地になっている土地です。
旗竿地は、相続や土地の開発によって大きな1つの土地を分割する際にできます。大きな土地を単純に切り分けてしまうと、道路に接しない土地ができることがありますが、建築基準法では、「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」という接道義務が定められています。そこで、2m以上の幅がある通路を作って道路とつなげると、結果として旗竿地ができるのです。
なお、正方形や長方形の土地を「整形地」と呼ぶのに対して、旗竿地や台形のように特殊でいびつな形の土地は「不整形地」と呼ばれ、整形地と比べて成約価格が低くなる傾向にあります。今回は、旗竿地が一般的に売れにくい理由や、旗竿地を売るためのポイントについて解説します。
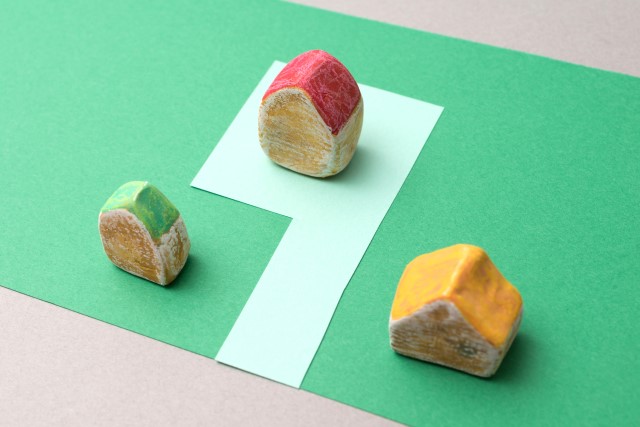
旗竿地が売れにくいと言われる理由4つ
旗竿地が売れにくい理由は主に以下の4つです。
・建て替えができない場合がある
・日当たりが悪い場合がある
・建物の取り壊しや、リフォームの経済的負担が大きくなりやすい
・私道が含まれる場合がある
それぞれ詳しく解説していきます。
建て替えができない場合がある
現行の建築基準法に適合していない旗竿地は、建物の建て替えができない場合があります。現行法では、道路に面する竿部分の間口は2m以上とされていますが、以前は1.8m以上が基準でした。そのため、改正前に建てられた旗竿地は、道路に接する部分が2mに満たない場合もあります。そのような改正前の土地に建物が建てられている場合、解体して家を建て替えることができない再建築不可物件となります。再建築不可物件は、一般的に買い手が見つかりにくくなりますが、対処法について後ほどご紹介します。
●再建築不可物件の売却について詳しくはこちら
日当たりが悪い場合がある
旗竿地は土地の性質上、周りを建物に囲まれることが多く、それにより光や風を遮られる場合があります。そのため、居住者の光熱費の負担が増えることがあります。リビングを2階に配置したり、吹き抜けや天窓を多用したりすることによって対策は可能ですが、建築コストがかかるので、旗竿地よりも整形地が選ばれるケースが多いのが現実です。
建物の取り壊しや、リフォームの経済的負担が大きくなりやすい
旗竿地のなかには、竿の部分が極端に狭く、取り壊しやリフォームの際に、大型車両が通れない土地があります。そのような土地の場合、機材をばらした状態で運び、現場で組み立てる方法を採用することが一般的です。また、資材に関しても近くの駐車場に停めてから運ぶ必要があり、人的コストがかさむことが多いでしょう。
私道が含まれる場合がある
旗竿地の竿となる部分は、隣人をはじめとするほかの所有者の私道である場合があります。その場合、私道部分の水道管工事や道路の補修をする際はその都度、私道の所有者全員の許可を取らなければなりません。そのような煩わしさや、竿の部分の所有者とのトラブルを避ける目的で旗竿地の購入をためらう方は多いでしょう。

旗竿地のメリット
売れにくいとされる旗竿地にもメリットはあります。売却活動の際に、積極的にアピールできるよう事前に知っておきましょう。旗竿地の主なメリットは以下の3つです。
・道路から離れているため騒音が少ない
・路地の部分を活用できる
・路地の面積によっては大きな家を建てられる
それぞれ詳しく解説していきます。
道路から離れているため騒音が少ない
旗竿地は土地の性質上、道路から離れた位置に家が建つため、通行人の声や車の走行音などの騒音が聞こえにくい傾向があります。さらに人目に付きにくく、プライバシーが守られる点も魅力的な要素でしょう。
路地の部分を活用できる
旗竿地の路地は駐車場として活用できる場合があります。その場合、路地の奥に駐車場のスペースを作らなくて済むので、居住空間を広く使えます。また、車を所有していない場合は、駐輪場に活用することも可能です。
路地の面積によっては大きな家を建てられる
家を建てるときには、敷地面積に対する建ぺい率や容積率によって制限がかかります。旗竿地の場合は、竿部分の面積も含むことで、旗部分だけの面積で換算した場合は建てられないような、大きな家を建てられる可能性があります。
このように売れにくいと言われている旗竿地にもメリットがあるので、売却を考えている方は、購入検討者にアピールできるようにしましょう。

旗竿地における売れる、売れない特徴
売れる旗竿地と売れない旗竿地の違いはどこにあるのでしょうか?ここでは、売れる旗竿地と売れない旗竿地の特徴について紹介します。売却を検討している方は、所有している土地と比べてみましょう。
売れる特徴
以下が売れる旗竿地の主な特徴です。
・日当たりがよい
・間口が広くて活用できる
・プライバシー対策がしてある
・立地がよい
売れない特徴
以下が売れない旗竿地の主な特徴です。
・私道が含まれている
・間口が狭い
・再建築できない
・竿の部分が長い
では、売れない特徴を持つ旗竿地を売れやすくするためにはどうすればよいのでしょうか?次は、売れにくい旗竿地を売れやすくする方法を解説します。

売れにくい旗竿地を売れやすくする方法
売れにくい旗竿地を売れやすくする方法は主に以下の3つです。
・セットバックの必要性を確かめる
・私道の所有者に交渉する
・隣の宅地の所有者への売却を検討する
それぞれ詳しく解説していきます。
セットバックの必要性を確かめる
所有している土地にセットバックの必要があるか確かめましょう。セットバックとは、道路に面した部分の敷地を、敷地側に向かって後退させ道路幅を広げることです。前述の通り、建築基準法では、「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と定められているので、幅員が4m未満の場合は敷地の一部をセットバックする必要があります。セットバックすることで道路幅が大きくなり、建物を建てる条件を満たせるため、建て替えを考えている方には有効です。
なお、幅員は自治体の役所に問い合わせるか、不動産会社へ調査依頼することで分かります。事前に確認しておきましょう。
私道の所有者に交渉する
竿部分に私道が含まれていることが原因で売れにくい場合は、私道の所有者に持ち分の購入や通行地役権の取得を事前に打診しておくことで問題が解決する場合があります。通行地役権とは、自分の土地の便益のために他人の土地を通行できる権利のことです。
私道の所有では、地主といった個人が所有しているケースと、その私道を使用する複数の人が持ち分を購入して共同で所有するケースが一般的です。特に、私道の所有者が地主をはじめとする個人の場合、所有者との関係性が悪くなると使用できなくなることがあります。そのため、所有者に私道を購入させてほしいと打診する際や、通行地役権の発行を依頼する際は慎重に行いましょう。
隣の宅地の所有者への売却を検討する
旗竿地がなかなか売れない場合、隣地の所有者への売却を検討するのも1つの方法です。隣人からすると、隣の旗竿地を購入し、所有する土地と合わせることで整形地に近付けられる場合があります。また、道路に接する長さが伸びて土地としての価値も上がると、隣人に購入してもらいやすくなるでしょう。

旗竿地の評価額を計算する方法
これまで見てきたように、旗竿地は整形地に比べて相場が下がる傾向にありますが、評価額はどうでしょうか?ここでは、計算方法から旗竿地の評価額の導き方について解説します。
旗竿地の評価額は以下の式で求められます。
評価額 = 路線価 × 補正率 × 土地面積
路線価とは、道路に面した1㎡あたりの土地価格を公表するもので、国税庁が毎年7月~8月に「路線価図・評価倍率表」において公表しています。旗竿地の評価額を出すには、路線価に土地の形状等に応じた補正率(画地補正率)を乗じて、まず単位地積当たり価額を求めます。この額に土地面積を乗じることで評価額が算出されます。
旗竿地の評価額計算に用いられる補正率は、旗竿地の形状や間口、奥行きの長さなど状況に応じて以下の4種類が用いられます。
| 補正率の種類 | 適用条件 |
|---|---|
| 奥行価格補正率 | 奥行き距離が極端に短い、長い |
| 奥行長大補正率 | 間口幅に対して奥行き距離が2倍以上ある |
| 間口狭小補正率 | 道路に面している間口が狭小である |
| 不整形地補正率 | 宅地の形状が整っていない |
ご紹介した補正率は、「0.9」や「0.88」のように「1」を切るケースが多く、その場合、整形地に比べると旗竿地の評価額は低くなります。
評価額が低いということは、相続税や固定資産税の金額も整形地に比べて低くなることを意味します。旗竿地の売却を考えている方は、そういったメリットを買い手にアピールできるでしょう。
●各補正率の詳しい説明や、数値はこちら
旗竿地売却で後悔しないためのコツ
旗竿地売却で後悔しないためのコツは主に以下の2つです。
・むやみに家を解体しない
・慎重に不動産会社を選定する
それぞれ注意点と併せて詳しく解説していきます。
むやみに家を解体しない
家を解体して更地にすると、固定資産税の住宅用地における特例措置の適用外になるので、土地にかかる固定資産税が上がります。たとえば、住宅用地は固定資産税評価額が最大で1/6に軽減されますが、更地にすると特例措置が受けられなくなります。そのため、売り出す前に家を解体するかどうかは、不動産会社に相談して慎重に検討しましょう。
●住宅用地及びその特例措置について詳しくはこちら
慎重に不動産会社を選定する
形状が特殊な旗竿地は、経験や実績のある不動産会社に任せられるかが売却の鍵になるでしょう。不動産会社を選ぶ際は、実績が豊富で、複雑な土地の扱いにも詳しい会社を見定め、査定を受けることが大切です。また、実際にどのような説明を受けるかで、旗竿地の売却にどれだけ親身になってくれるかを判断できるでしょう。
三井のリハウスでは、100万件以上の取引実績に基づく、精度の高い査定を無料で行っています。旗竿地売却をご検討の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
●無料査定のお申し込みはこちら

旗竿地が売れないときは三井のリハウスへ!
ここまでお伝えしてきた通り、旗竿地は一般的な宅地に比べて買い手が付きにくかったり、売却まで時間がかかったりすることがあります。しかし、売却戦略をしっかり立てることで売れる見込みはあります。
旗竿地の売却は、経験豊富なプロに相談することをおすすめします。三井のリハウスでは、豊富な知見を生かした売却プランのご提案や無料査定など、不動産売却に関する幅広いサポートを行っています。「旗竿地を売却したいがスムーズに売却できるか心配」「旗竿地が売れなくて困っている」という方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
●無料査定のお申し込みはこちら
●リハウスAI査定はこちら


監修者:ファイナンシャル・プランナー 大石泉
株式会社NIE.Eカレッジ代表取締役。CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を保有。住宅情報メディアの企画・編集などを経て独立し、現在ではライフプランやキャリアデザイン、資産形成等の研修や講座、個別コンサルティングを行っている。











