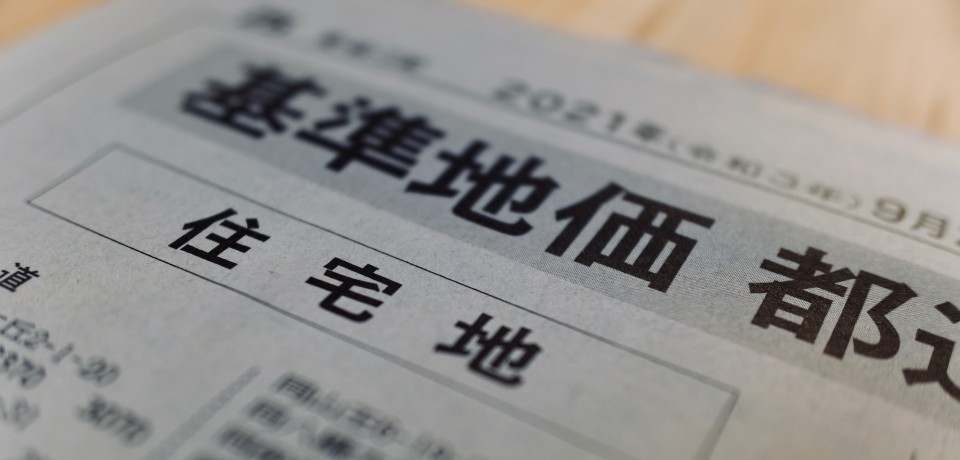
基準地価とは?公示地価・路線価との違いや調べ方を解説
基準地価とは、都道府県から発表される、基準地1㎡あたりの標準価格のことをいいます。幅広い土地取引で不動産価格の目安として用いられるため、土地を売買するうえで重要な指標です。そこで今回は、公示地価・路線価との違いや、基準地価が掲載されているサイトなどについて解説します。
基準地価とは
基準地価とは、都道府県が選定した基準地1㎡あたりの標準価格です。各都道府県が国土利用計画法にもとづき、毎年7月1日時点の基準価格を判定し、9月下旬頃に発表されます。
基準地価は、一般的な土地取引の場面で価格の指標として用いられるため、所有している土地や購入したい土地の適正価格が知りたいときに役立ちます。ただし、基準地価は土地を更地として評価した場合の価格であり、建物の価値を考慮していない点には注意しましょう。
基準地は住宅や商業地、工業地などに区分されており、2024(令和6)年は全国21,436地点が評価の対象となりました。
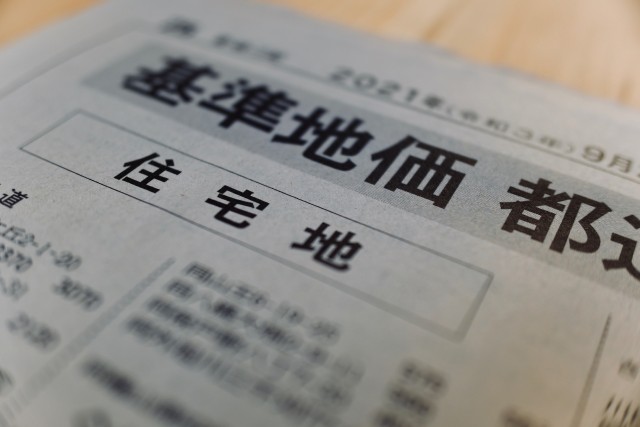
基準地価と公示地価・路線価の違い
土地の価格を調べる際に参考になる情報として、基準地価のほかに、公示地価と路線価が挙げられます。それぞれの価格と基準地価との違いについて、以下で詳しく説明します。
公示地価との違い
公示地価とは、2名以上の不動産鑑定士が全国の標準地を鑑定・評価した結果にもとづいて、国土交通省が公表する土地の価格です。評価の対象となる土地である標準地は、基本的に都市計画区域内から選定されます。
基準地価と公示地価の主な違いは以下の表の通りです。
| 比較項目 | 基準地価 | 公示地価 |
|---|---|---|
| 基準日 | 7月1日 | 1月1日 |
| 公表時期 | 9月下旬 | 3月下旬 |
| 公表機関 | 都道府県 | 国土交通省 |
| 対象地域 | 都市計画区域内外 | 基本的に都市計画区域内 |
公示地価が1月1日を基準に算定されるのに対して、基準地価はその半年後の7月1日を基準としています。そのため、公示地価と基準地価は最新の地価動向を補完し合う存在といえます。
また、基準地価の評価対象は都市計画区域の外も含んでいるのに対し、公示地価の評価対象は主に都市部です。そのため、基準地価は公示地価と違い、林地のような都市部以外の地域でも適正価格を知ることができます。なお、国や都道府県から毎年公表される公示地価と基準地価は、合わせて「公示価格」と呼ばれることもあります。
●公示価格に関する詳しい記事はこちら
路線価との違い
路線価とは、路線(道路)に面する土地の1㎡あたりの単価を指すもので、毎年国税庁が発表しています。路線価には相続税路線価と固定資産税路線価がありますが、多くの場合で、相続税や贈与税を算出するために用いる相続税路線価を指します。
基準地価と路線価の主な違いをまとめた表は以下の通りです。
| 比較項目 | 基準地価 | 路線価 |
|---|---|---|
| 基準日 | 7月1日 | 1月1日 |
| 公表時期 | 9月下旬 | 7月初旬 |
| 公表機関 | 都道府県 | 国税庁 |
| 対象地域 | 都市計画区域内外 | 全国の民有地(路線価地域) |
どちらも地価を表していますが、基準地価は一般の売買取引に用いられます。一方、路線価は主に土地にかかる相続税や固定資産税を算出するために用いられます。
路線価は基準地価や公示地価といった公示価格をもとに定められており、相続税路線価は公示価格の約80%程度、固定資産税路線価は約70%程度の価格です。

基準地価の調べ方
国土交通省のサイトである「不動産情報ライブラリ」を使えば、地図上で基準地・標準地や、その基準地価・公示地価を確認できます。周辺の不動産の取引価格も調べられるため、情報が集めやすく、利便性が高いことが特徴です。
また、基準地価は各都道府県のホームページや役所・役場でも調べられます。例として、東京都の場合は財務局のサイトから各年度の基準地価を知ることができます。所有する土地がある自治体で確認することが望ましいでしょう。
●東京都基準地価格はこちら

【2024(令和6)年】最新の基準地価の動向
国土交通省の土地政策審議官グループが、2024(令和6)年度の全国の基準地価を「令和6年都道府県地価調査の概要」(※1)にまとめています。それによると、景気が緩やかに回復に向かっているなか、地価は全国的に上昇傾向です。三大都市圏では、価格の上昇が続き、その上昇幅も大きくなっています。また、地方圏も昨年に引き続き上昇し、特に商業地で地価の上昇が見られます。
| 基準地価の変動率 | 全用途平均 | 住宅地 | 商業地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | |
| 全国 | 1.0% | 1.4% | 0.7% | 0.9% | 1.5% | 2.4% |
| 三大都市圏 (東京圏、大阪圏、名古屋圏) | 2.7% | 3.9% | 2.2% | 3.0% | 4.0% | 6.2% |
| 地方圏 (札幌市、仙台市、広島市、福岡市など) | 0.3% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.9% |
さらに詳しく見ていくと、主要都市の商業地の地価上昇を支えているのは、都市中心部や観光地、再開発が進む地域における店舗やホテル、オフィスによる需要です。
住宅地については、低金利環境による安定した需要にもとづく地価の上昇が継続しています。特に、大都市圏中心部やリゾート地、新幹線開業で交通利便性が高まった地域で上昇傾向が見られました。具体的な地域としては、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県などの上昇率が大きく、沖縄県の上昇率が最大です。
全体的に地価は上昇傾向にあり、土地を高い価格で売却できる可能性が高まっています。また、基準地価の順位としては住宅地・商業地ともに東京都の港区や千代田区、中央区といった都心部がトップ5を占めています。
●土地の売却相場に関する詳しい記事はこちら

基準地価と実勢価格の関係
基準地価は土地を更地としたときの適正な価格を表す指標であり、実際に取引された価格である実勢価格とは異なります。なぜならば、実勢価格は売買が成約した当時の経済状況や、当事者の事情を反映しながら決まるためです。さらに、実勢価格は基準地価や公示地価などを参考にしつつ、土地の用途や建物部分の価値なども考慮して決まります。
なお、基準地価や公示地価を知ることで実勢価格の目安を算出できます。実勢価格の目安は公示地価や基準地価を1.1倍したものとされており、その計算方法は以下の通りです。
基準地価・公示地価×土地面積×1.1=目安の実勢価格
ただし、都市部の実勢価格は変動しやすく、基準地価や公示地価の1.5倍~2倍になることもあるため注意しましょう。
●実勢価格の算定方法に関する詳しい記事はこちら

基準地価を理解して土地の価格設定に役立てよう
基準地価は、土地売買の際に価格のおおまかな目安として活用されています。気になっている不動産がある場合は、購入前に適正な価格かどうかを判断する材料にしましょう。また、自身が所有する土地を売却する際にも、提示された査定額が正しいか判断したり、売り出し価格を決めたりするうえで役に立ちます。
不動産の売却を考えている方は、基準地価や公示地価を参考にしつつ、不動産会社に査定を依頼して売却活動を慎重に進めましょう。三井のリハウスでは、担当者が豊富な実績にもとづく知見を生かして無料査定や売却活動のサポートを行っています。不動産の売却を検討している方は、ぜひ三井のリハウスにご相談ください。
●無料査定はこちら
※1出典:令和6年都道府県地価調査の概要,国土交通省 土地政策審議官グループ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001762894.pdf
(最終確認:2025年1月17日)


監修者:三上隆太郎
株式会社MKM 代表取締役
大手ハウスメーカーにて注文住宅の受注営業、家業の建設会社では職人として従事。
個人向け不動産コンサルティング会社のコンサルタントやインスペクターを経験し、中古+リノベーションのフランチャイズ展開、資格の予備校にて宅地建物取引業法専属講師など、不動産業界に幅広く従事。
https://mkm-escrow.com/











