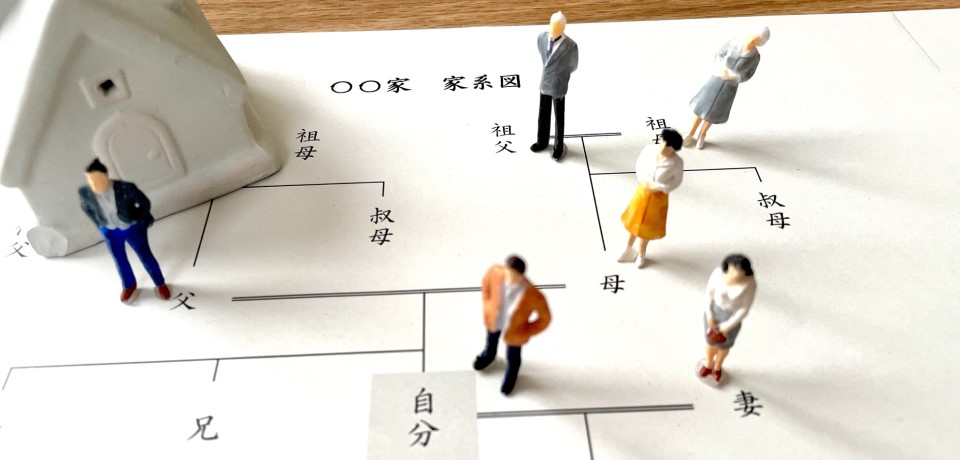
相続した不動産を売却して分割する方法とは?メリットと注意点を詳しく解説
相続不動産を売却して分割する方法には、「換価分割」「代償分割」の2種類があります。この記事では複数人での相続をトラブルなく進めたい方に向けて、各方法のメリットと注意点、遺産分割協議書の書き方などを解説します。
目次
相続不動産を売却して分割する方法
遺産のなかには現金や預貯金のように、1円単位で分割できるものばかりではなく、家やマンションといった不動産のように細かく分けられないものも存在します。では、相続した不動産は分割できないのでしょうか?
複数の相続人で不動産を相続した場合、分割するには次のような方法があります。
・現物分割…「不動産をAが相続、株式をBが相続」あるいは「土地を分筆する」などのように現物のまま分配する
・換価分割…不動産を売却した代金を相続人間で分け合う
・代償分割…1人が不動産を相続し、ほかの相続人に代償金を支払う
・共有分割…不動産を共有名義とし、相続人同士で所有する
ただし上記のうち、現物分割は実際には難しい場合が多く、共有分割は後々トラブルが起こりやすいといわれています。そのため、不動産を売却することが決まっている場合は、換価分割か代償分割の2つから選ぶことが一般的です。
この記事では、複数人で相続した不動産を売却して分割したい方に向けて、2つの分割方法の詳細や遺産分割協議書の書き方などを解説します。
まずは換価分割、代償分割それぞれのメリットと注意点を見ていきましょう。
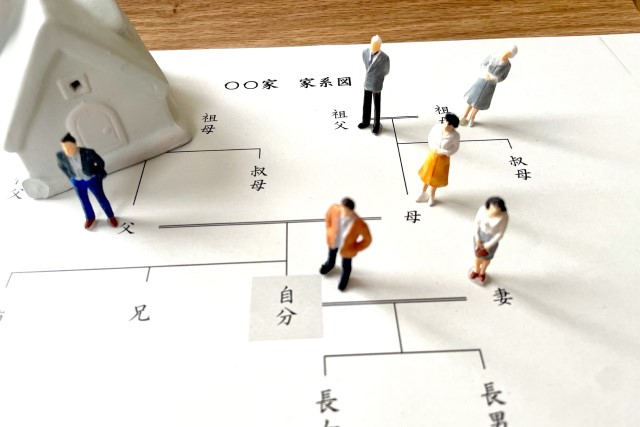
相続した不動産を換価分割するメリットと注意点
換価分割のメリットは、公平な遺産分割がしやすい点にあります。不動産売却で得た代金を分けるだけというシンプルで明解な方法なので、相続人間でのトラブルが起こりにくいのが特長です。また、現金を受け取れるので、相続税の資金確保にも役立つ方法といえるでしょう。
一方、不動産売却を焦ったり、効果的な売却活動ができなかったりすると、安値で手放して相続人全員が損をしてしまう恐れがある点には注意が必要です。また、不動産売却には諸費用がかかるほか、プラスの譲渡所得が発生すると所得税や住民税などを課税されることもあらかじめ理解しておきましょう。

相続した不動産を代償分割するメリットと注意点
不動産売却を前提とした代償分割のメリットは、代償金を確保しやすいことにあります。代償分割では代償金の用意が必要ですが、売却について相続人の間で合意していれば、売却代金を得てから代償金を支払うことも可能です。ただし、その旨は遺産分割協議書に記載しておく必要があるので忘れないようにしましょう。
注意したいのは、遺産分割協議の際に代償金の金額を決めなければならないことです。換価分割では売却代金が確定してから公平に分配できますが、代償分割の場合は売却前に金額を決めることになります。そのため、代償金の金額を決める際は、査定を受けて売却見込額を把握したうえ、売却にかかる費用、譲渡所得にかかる税金も含めて検討することが大切です。

相続不動産を売却して分割したときの税金は?
相続した不動産を売却した場合、換価分割と代償分割では税金の発生の仕方が異なります。ここでは、税金の仕組みについて、節税に利用できる特例と併せて解説します。

換価分割の税金
換価分割の場合、不動産売却で得た譲渡所得に対して相続税を課せられることはありません。なぜなら相続税とは、相続が始まった時点の相続財産の評価額に対して課せられるものであり、換価分割して得た売却代金と評価額は異なるためです。ただし、相続不動産を売却し、プラスの譲渡所得が発生した場合には所得税や住民税などが課せられます。その場合、相続人各自で確定申告を行い、納税しましょう。
代償分割の税金
代償分割の場合、現金で代償金を支払っても、譲渡所得に関する税金や贈与税は課税されません。ただし、現金の代わりに所有する不動産を代償として渡した場合は、譲渡する側に譲渡所得に関する税金が発生する場合があります。なぜなら、不動産の取得費よりも代償分割したときの時価のほうが高かった場合、差額を譲渡所得と見なされるためです。また、代償分割して代償金を支払う旨を遺産分割協議書に記載していないと、贈与と見なされ受け取った側に贈与税が課税されてしまうこともあるため注意しましょう。

利用できる特例
相続不動産を売却して分割する場合、以下の特例を活用すると税金を節税することができます。
・居住用財産の3,000万円控除
・小規模宅地等の特例
・相続空き家の3,000万円控除
3つの特例について詳しく解説しましょう。
居住用財産の3,000万円特別控除
相続人が「居住用財産の3,000万円特別控除」の要件を満たす場合は、譲渡所得に関する税金を節税できます。たとえば、被相続人(亡くなった人)と同居していた相続人Aが代償分割で不動産を相続し、その後売却した場合、譲渡所得から3,000万円の控除を受けられます。つまり、税金を差し引いた後に残る手取り金額がその分大きくなるということです。
一方で換価分割の場合、特例の要件を満たす相続人と満たさない相続人がいると、控除を受けられるのは要件を満たす人のみとなります。たとえば、被相続人と同居していた相続人A、別居していた相続人Bで相続不動産を換価分割した場合、Aのみが特別控除の対象となり、Bは対象外となります。
このように、相続人の状況や分割方法によって適用できる範囲が変わってくるので慎重に検討しましょう。
●居住用財産の3,000万円特別控除に関する詳しい記事はこちら
小規模宅地等の特例
代償分割では「小規模宅地等の特例」を活用できる場合があります。小規模宅地等の特例とは、被相続人が所有していた宅地の評価額を最大80%下げられるという制度です。要件を満たす相続人がその不動産を相続して代償分割すれば、宅地の評価額を下げられるため、相続税の節税につながります。
相続空き家の3,000万円特別控除
被相続人が亡くなって空き家になった家を換価分割のために売却する場合、要件を満たしていれば「相続空き家の3,000万円特別控除」を活用できます。相続人1人につき、譲渡所得から3,000万円が控除されるので、大きな節税につながる特例です。
なおこちらの特別控除は、被相続人が生前1人で住んでいた家を対象としているため、相続人が居住するマイホームを対象としている居住用財産の3,000万円特別控除とは、要件が異なります。居住用財産の3,000万円特別控除の要件を満たしていない場合でも、こちらの特別控除が活用できる可能性があるので確認してみましょう。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議とは、複数の相続人が全員立ち会いのもと、遺産をどのように分割するかを決めることです。相続不動産を売却して分割する場合、換価分割か代償分割かを話し合いで決定し、遺産分割協議書を作成する必要があります。ここでは、それぞれの遺産分割協議書の書き方を紹介します。

換価分割の場合
換価分割の場合、遺産分割協議書は相続登記を「共同登記」または「単独登記」のどちらで行うかによって書き方が異なります。共同登記とは、相続不動産の名義を被相続人から相続人全員に変更することを指し、単独登記は、被相続人の名義から相続人代表者1人の名義に変更することを指します。
共同登記の場合
共同登記の場合は、「次の不動産は換価分割を行うため、相続人A、相続人B、相続人Cがそれぞれ3分の1の割合で共有取得する」「相続人A、相続人B、相続人Cは共同して前項の不動産を売却し、売却代金から売却にかかる費用全てを控除した残金を、それぞれの共有持分割合に従い取得する」というように記載しましょう。
単独登記の場合
単独登記の場合は、「次の不動産は、換価分割を行うため相続人Aが取得する」「相続人Aは前項の不動産を売却し、売却代金から売却にかかる費用全てを控除した残金を以下の割合で分配する」として、「相続人A、相続人B、相続人Cそれぞれ3分の1ずつ」と割合を書き添えます。
共同登記の場合、売却の際の手続きを相続人全員で行う必要があり、単独登記と比較すると手間が多くなります。一方単独登記の場合、相続人が1人であるため売却できるまでの固定資産税や維持費も全て1人が負担しなければいけません。それぞれの注意点を把握したうえで、ご自身や親族の状況・希望に合った方法を選びましょう。
代償分割の場合
代償分割の場合は、代償金をいつどのように、誰に支払うのかを明記する必要があります。現金で支払う場合、「相続人Aは次の不動産を取得する」「相続人Aは前項の不動産を取得する代償として、相続人B、相続人Cに対して金◯◯◯万円を◯◯年◯◯月◯◯日までに銀行振込で支払う」というように記載します。また、代償金の支払いは相続人同士が承諾すれば分割払いも可能なので、必要な際は分割払いの期間と支払い日も書き添えるようにしましょう。
相続不動産の売却・分割はプロに相談
相続不動産を売却して分割する場合は、税金の仕組みや活用できる特例などを踏まえたうえで、換価分割、代償分割のどちらが有利かを検討するのがおすすめです。
しかし、税金のシミュレーションは複雑なうえ、初めての不動産相続・売却には不明点が付きものです。悩んだ際は、税理士や不動産会社などのプロに相談するとよいでしょう。
三井のリハウスでは、相続不動産の売却をサポートしています。まずは不動産査定を受けてどれくらいの価格で売却できそうかを把握することで、換価分割の場合も代償分割の場合も資金計画を立てやすくなりますよ。
三井のリハウスでは、豊富な実績を生かした精度の高い無料査定を実施しています。相続不動産の売却をご検討の方は、お気軽にご利用ください。


監修者:ファイナンシャル・プランナー 大石泉
株式会社NIE.Eカレッジ代表取締役。CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を保有。住宅情報メディアの企画・編集などを経て独立し、現在ではライフプランやキャリアデザイン、資産形成等の研修や講座、個別コンサルティングを行っている。
https://www.izumi-ohishi.co.jp/profile.html










