
鉄骨造の耐用年数は?実際の寿命との違いや減価償却について解説
鉄骨造の耐用年数の表し方には数種類あり、それぞれ意味が異なります。この記事ではマイホームにかかわる耐用年数の種類をご紹介するほか、減価償却費の計算方法、建物の寿命を延ばすためのポイントも解説します。
目次
鉄骨造の耐用年数とは?
鉄骨造(S造)とは、建物の柱や梁などの骨組みに鉄を用いる構造を指します。丈夫で長持ちするイメージがありますが、耐用年数はどのくらいなのでしょうか?
建物の耐用年数の表し方には、主に以下の3つがあります。
・法定耐用年数
・物理的耐用年数
・経済的耐用年数
それぞれの意味について、順番に解説していきます。
法定耐用年数
法定耐用年数とは、資産の使用可能期間を、その構造や用途にもとづいて国が定めたものです。会計処理上の「減価償却」を行う際の指標にもなります。減価償却とは、資産の価値が時間の経過とともに減少するという考え方で、その減少分は「減価償却費」という経費として計上できます。なお、マイホームでは、非事業用資産の法定耐用年数を用いて減価償却費を算出します。
鉄骨造の建物の法定耐用年数は、鉄骨の厚さと用途によって異なり、マイホーム(非事業用資産)の場合は以下の通りです。
| 鉄骨の厚さ | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 3mm以下 | 28年 |
| 3mm超4mm以下 | 40年 |
| 4mm超 | 51年 |
法定耐用年数はあくまでも税制上の数字であり、実際にその年数が建物の寿命になるわけではありません。この年数をすぎても多くの場合で建物の使用は可能ですが、いくつか注意点があります。
法定耐用年数を用いた減価償却の計算方法については、後ほどご紹介します。
物理的耐用年数
物理的耐用年数とは、建物が物理的に使用できなくなるまでの期間を指します。環境や維持管理の状況によって左右され、適切に維持管理されている建物は長く使うことができます。
目安として、鉄骨造の物理的耐用年数は、適切なメンテナンスができていれば約50年~60年程度です。
経済的耐用年数
経済的耐用年数とは、建物の経済的価値がなくなるまでの期間を指します。減価償却費の計算に使われる法定耐用年数とは異なり、市場での価値にもとづいて算出された年数です。
また、経済的耐用年数も建物の使用状況や維持管理の状態に左右されます。所有している鉄骨造の建物の価値を知りたい方は、不動産会社に査定を依頼するのがおすすめです。三井のリハウスでも査定を承っておりますので、まずはお問い合わせください。
●三井のリハウスの不動産査定はこちら
●不動産査定の方法や流れについてはこちら

鉄骨造の実際の寿命は長い?
建物の実際の寿命に近い意味を持つ物理的耐用年数は、鉄骨造で約50年~60年程度が目安です。実際の寿命は、使用状況や維持管理の状態に左右されるため、上記はあくまで目安ですが、引越しや建物の購入を検討している方は参考にしてください。

鉄骨造の減価償却費を計算する方法
不動産を売却して譲渡所得(利益)が発生した場合は、減価償却費を計上することで節税につながります。
減価償却費の計算方法には、「定額法」と「定率法」の2種類があります。特に届け出がなければ「定額法」で、マイホームの場合は非事業用資産の法定耐用年数を用いて次の公式をもとに減価償却費を算出します。
減価償却費(定額法)=建物購入代金×0.9×償却率×経過年数
なお、鉄骨造のマイホームにおける法定耐用年数と償却率は以下の通りです。
| 鉄骨の厚さ | 法定耐用年数 | 償却率 |
|---|---|---|
| 3mm以下 | 28年 | 0.036 |
| 3mm超4mm以下 | 40年 | 0.025 |
| 4mm超 | 51年 | 0.020 |
●具体的な計算例についてはこちら

鉄骨造の寿命を延ばすには?
ここでは、鉄骨造の建物を購入した方、または購入を検討している方に向けて、建物の寿命を延ばすために気を付けるべきことをご紹介します。
土地や周辺環境の特徴に応じた対策を行う
土地の特徴を把握することで、建物の寿命を延ばすために必要な対策が分かります。たとえば海に近いエリアでは、潮風によるサビや傷みが生じやすいので塩害対策が必要です。また、地盤が軟弱な地域では、建物を建てる前に地盤改良を行うことで寿命が延びる場合もあります。
定期的なメンテナンスを行う
鉄骨造の建物は、定期的なメンテナンスを行うことによって、劣化を防ぎやすくなります。鉄骨造は木造と比べて丈夫なイメージがありますが、屋根の防水層や外壁の接合部に存在する微細な亀裂から雨水が浸入し、鉄骨の柱や梁をさびさせる恐れがあるためです。定期的に専門業者やハウスメーカーの点検を受けるようにすれば、劣化が進む前に適切な対策を取れるでしょう。
また、鉄骨のサビを防ぐためには、日頃から窓の結露や湿気などにも気を付けましょう。
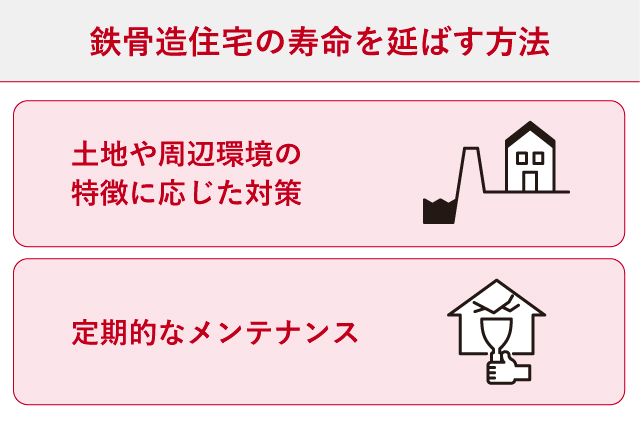
鉄骨造が法定耐用年数を超過した場合の注意点
法定耐用年数は建物の実際の寿命と異なり、超過しても利用できなくなるわけではありません。しかし、法定耐用年数を超えた建物は老朽化が進んでいるため、修繕やメンテナンスなどの維持費が多くかかる場合もあるため、注意が必要です。
法定耐用年数を超過した鉄骨造の建物はどうすればいい?
所有している鉄骨造の建物が法定耐用年数を超過している場合、どうしたらよいのでしょうか?対処法としては以下の2つがあります。
・修繕を行う
・売却する
1つずつ見ていきましょう。
修繕を行う
法定耐用年数を超えてしまっても、適切な修繕やリフォームを行えば、建物の物理的耐用年数や経済的耐用年数を延ばすことはできます。売却を検討している場合は物件のイメージアップにつながるうえ、建て替えに比べて費用が抑えられるのがメリットです。ただし、マンションでは共用部分に影響を及ぼす改修工事は個人で行えないことが一般的です。修繕やリフォームを希望する場合はまず管理会社に相談し、可能な工事内容について確認しましょう。
売却する
法定耐用年数を超えた物件は維持費がかかりやすいため、売却も選択肢の1つです。売却の場合、以下の方法があります。
・そのままの状態で売却する
・不動産会社に買い取ってもらう
・更地にして売却する
法定耐用年数を超過した物件は買い手が見つかりにくく、売却に時間がかかるケースも多いため、販売経験の豊富な不動産会社に相談することが大切です。また、一戸建ての場合は更地にしてから売却したほうがよいケースもありますが、建物の解体には費用や時間がかかります。そのため、まずは査定を依頼し、建物の市場価値を把握してから解体が必要かどうかを検討するとよいでしょう。
●不動産査定についてはこちら

不動産売却は三井のリハウスにお任せ
建物の耐用年数には種類があり、それぞれ意味が異なりますが、いずれも超過すると売買しにくくなるというリスクが生じます。
三井のリハウスでは、豊富な取引実績を生かして売却をサポートしています。ご所有の物件に現時点でどのくらいの価値があるのか気になる方は、無料査定をお試しください。ほかにも、お客さまそれぞれのお悩みやご希望に応じた売却プランも提案いたします。鉄骨造の家の売却をご検討中の方は、ぜひ一度三井のリハウスへお気軽にお問い合わせください。
●無料査定のお申し込みはこちら
●リハウスAI査定はこちら


監修者:ファイナンシャル・プランナー 大石泉
株式会社NIE.Eカレッジ代表取締役。CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を保有。住宅情報メディアの企画・編集などを経て独立し、現在ではライフプランやキャリアデザイン、資産形成等の研修や講座、個別コンサルティングを行っている。










